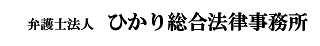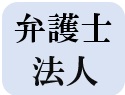婚姻届出後同居しないままの状態でいる夫婦の婚姻費用分担金
1 民法第760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。
実務上はこの規定を根拠に、別居中の夫婦において、収入の少ない権利者配偶者から収入の多い義務者配偶者に対して婚姻費用分担請求が行われることが多くあります。
そして、具体的分担額の決定には、いわゆる算定表が活用されているところです。
このような婚姻費用分担義務は、民法第752条が、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定していることと同じく、夫婦間の生活保持義務と考えるのが一般的です。
それでは、そもそも婚姻届出後、同居したことがない夫婦間においても、婚姻費用分担義務が生じるのでしょうか。
今回は、実際にこれが争われた近時の事例について考えてみたいと思います。
2 事案をごく簡略化しますと以下のとおりです。
妻(婚姻届出時37歳)と夫(婚姻届出時41歳)は、交際開始から約2か月後に婚姻の届出をしましたが、婚姻の届出後も週末に会うことは繰り返したものの同居しないままの状態が続き、届出から約2か月後に妻が同居を拒否したため、その後別居したまま会わなくなりました。
なお、妻は父母とともに実家に居住し、住所地を事業所として行政書士業を自営しており、夫は借家に居住して広告代理店に勤務しており、夫の方が収入が多い状態でした。
かかる当事者間で妻から婚姻費用の分担を求める家事調停が申し立てられ、調停不成立となったため、審判手続に移行して裁判所の判断が下されました。
3 横浜家庭裁判所令和4年6月17日審判は、本件の経緯の認定や婚姻費用分担義務の趣旨の検討を行った上で、次のように述べて妻の申立てを却下しました。
「申立人(注:妻)は、相手方(注:夫)と婚姻後も一度も同居しないまま、相手方との同居を拒んだ結果、相手方との夫婦生活が成立せず、婚姻前と同様に、両親とともに実家に暮らして行政書士業を続けている。申立人の相手方へ宛てた手紙での発言に照らすと、申立人が相手方との同居を拒む主たる理由は、相手方の支配欲や、夫婦観、人生観が基本的に申立人と相容れないことにあると認められる。そうすると、申立人と相手方が夫婦としての共同生活を始めることは、水と油のように元々無理なことであって、互いに相手の性格傾向や基本的な夫婦観、人生観を理解するのに十分な交流を踏まえていれば、そもそも当事者間で婚姻が成立することもなかったと推認することができる。言い換えると、当事者間の婚姻は余りに尚早の婚姻届出であって、本件において当事者間の夫婦共同生活を想定すること自体が現実的ではないということができる。
以上の事実関係の下では、当事者間で婚姻が成立しているとはいえ、通常の夫婦同居生活開始後の事案のような生活保持義務を認めるべき事情にはないというべきである。申立人は、現在の申告所得は相手方に及ばないものの、高い学歴と資格を有し、働く意欲も高いため、潜在的な稼働能力が同年代の平均的な労働者に比べて劣るとは考えにくく、婚姻前と同様に自己の生活費を稼ぐことは可能であって、具体的な扶養の必要性は認められないから、相手方に婚姻費用分担金の支払をさせる具体的な必要は認められない。」
かかる審判で注目されるのは、同居しないままでの本件では当事者間の夫婦共同生活を想定すること自体が現実的ではないとし、生活保持義務、具体的な扶養の必要性を否定していることです。
これに対して妻が即時抗告したため、抗告審の判断が下されました。
4 東京高等裁判所令和4年10月13日決定は、上記の原審判を取り消して、夫に婚姻費用分担義務を認め、婚姻費用分担金の支払を命じました。
東京高裁は、本件の事実関係について、
「互いに婚姻の意思をもって婚姻の届出をし、届出後直ちに同居したわけではないものの、互いに連絡を密に取りながら披露宴や同居生活に向けた準備を着々と進め、勤務先の関係者にも結婚する旨を報告して祝福を受けるなどしつつ、週末婚あるいは新婚旅行と称して、毎週末ごとに必ず、生活を共にしていた」
とし、
「抗告人(注:妻)と相手方(注:夫)の婚姻関係の実態がおよそ存在しなかったということはできず、婚姻関係を形成する意思がなかったということもできない。」
と認定しました。
そして、婚姻費用分担義務について、
「婚姻という法律関係から生じるものであって、夫婦の同居や協力関係の存在という事実状態から生じるものではないから、婚姻の届出後同居することもないままに婚姻関係を継続し、その後、仮に抗告人と相手方の婚姻関係が既に破綻していると評価されるような事実状態に至ったとしても、前記法律上の扶助義務が消滅するということはできない。もっとも、婚姻関係の破綻について専ら又は主として責任がある配偶者が婚姻費用の分担を求めることは信義則違反となり、その責任の程度に応じて、婚姻費用の分担請求が認められない場合や、婚姻費用の分担額が減額される場合があると解されるものの、本件においては、仮に、抗告人と相手方の婚姻関係が既に破綻していると評価されるような事実状態にあるとしても、その原因が専ら又は主として抗告人にあると認めるに足りる的確な資料はない。」
としました(その上で具体的分担額を判断しています。)。
なお、当該東京高裁の決定は確定しています。
5 以上のように、原審判と抗告審の決定は結論を反対のものとしました。
原審判は、同居しないままの本件夫婦について、いわば民法第760条の予定する範囲外であるとの扱いをしたと考えられ、一方で抗告審は、婚姻費用分担義務は婚姻という法律関係から生じるものであって、夫婦の同居や協力関係の存在という事実状態から生じるものではないとして、不合理な事案では信義則による修正を図れば足りるというスタンスであると思われます。
このような判断の違いは、事実状態を重視するのか、法律関係から生じる義務であることを重視するのかの違いに基づくといえると思われますが、婚姻や家族の形が様々である社会になっていこうとしている現在、抗告審のような、法律関係を重視し一般条項で修正を図る方法が妥当であるのかは、今後より悩ましくなっていくようにも思われます。
以上
問い合わせるにはこちら