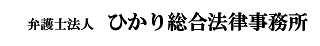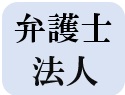憲法
1 安保関連法とは
安保関連法とは、主に以下の内容を指しています。
A 集団的自衛権の容認―自衛隊法及び武力攻撃事態法を改正して、これまでは、自衛権の発動は我が国が直接攻撃された場合だけに限定されていたが、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立の危機が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)」を新設し、その場合にも「自衛権」が発動できるようにした。
B 自衛権発動の地理的制約の撤廃―周辺事態法を改正して、これまでは自衛権の発動は場所的に我が国だけに制約されていたがその地理的制約を取り外し、世界中どこでも発動できるようにした。
C 非戦闘地域の概念の変更―周辺事態法を改正して、弾薬の提供、発信準備中の戦闘機への給油等の支援をする場所について、従来「現に戦闘が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われていることがないと認められる地域」であったのを「現に戦闘が行われている現場以外の場所」に拡大した。
2 集団的自衛権についての憲法解釈の閣議決定
2014年7月1日、安倍内閣は、集団的自衛権の行使が憲法上許されないとの1981年の政府見解を変更し、以下の要件の下に集団的自衛権の行使が憲法上許されるとの閣議決定を行いました。
Ⅰ 密接な関係にある他国への武力攻撃で我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。
Ⅱ 我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない。
Ⅲ 必要最小限度の実力行使。
3 集団的自衛権についての従来の政府見解
集団的自衛権についての従来の政府見解は、以下のとおりでした。
「国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されてもいないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。
我が国が、国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上、当然であるが、9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。」(1981年5月29日 政府答弁)
「政府の憲法解釈はそれぞれ論理的な追求の結果示されてきたものであり、自由にこれを変更することができるような性質のものではない。」(平成8年2月27日 衆予算委)
「仮に集団的自衛権の行使を憲法上認めたという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然取らざるを得ない。」(昭和58年2月22日 衆予算委)
4 山口繁元最高裁長官(平成27年9月3日 朝日新聞朝刊)
今回の安保関連法の改定について、山口繁元最高裁判官は以下のように批判しています。
「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」、砂川判決について「当時の最高裁は集団的自衛権について意識していないし、この裁判で集団的自衛権の行使が憲法上許されるか否かを判断する必要もなかった」、安倍内閣が平成26年7月1日に解釈変更を閣議決定したことについて「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない、憲法9条の抑制機能について考えていない」
その他にも、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏、宮崎礼壱氏も同様の論調で批判しています。
小林節(慶応大学)、長谷部恭男(早稲田大学)、木村草太(首都大学東京)等の錚々たる憲法学者の圧倒的多数が、安保関連法の改定を「違憲」であると断じています。
5 集団的自衛権合憲説の論理
集団的自衛権が合憲であるとの説は、以下のような理由をあげています。
Ⅰ 憲法に集団的自衛権の規定がない。
Ⅱ 国際法で集団的自衛権が認められている。
Ⅲ 自衛のための必要最小限度の武力行使に集団的自衛権の行使も含まれる。
Ⅳ 砂川事件判決(この判決は、我が国が日米安保条約によって米軍駐留を認めることを合憲としたもので、憲法9条2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうもので、結局我が国自体の戦力を指し、外国の軍隊は憲法の禁止する戦力に該当しない、と判示したもの)
6 歴史的に憲法と民主主義は直接関係ない
ところで、歴史的に見て、憲法や議会制度と民主主義とはどのような関係にあるのでしょうか。結論からいえば、直接的には関係がない、と言えます。憲法や議会制度は民主主義が実現されるよりはるか前に作られ、憲法や議会制度が民主主義を取り入れたのです。
7 マグナカルタ(憲法)
1215年6月15日にマグナカルタが公布されました。ジョン王はフランスとの戦争のために、貴族や教会に無制限に税金を課しました。それに対して貴族が、王権が「既得権益と慣習法を破っている」ことを理由として63ヶ条の「契約」を作ってジョン王に署名させました。その内容は王といえども法(慣習法)の下にあり、王といえども法(慣習法)を破った場合には反乱に訴えることができる、というものです。
特に重要な項目は以下のとおりです。
教会は国王から自由である(第1条)
王の決定だけで戦争協力金などの名目で税金を集めることはできない(12条)
ロンドンほか自由市は交易の自由を持ち、関税を自ら決められる(13条)
国王が議会を招集しなければならない場合を定める(14条)
自由民は国法か裁判によらなければ自由や生命、財産を侵されない(38条)
以上で述べたように、マグナカルタの目的はあくまで「伝統を守る」という1点にあったのです。しかもそれは一部の特権階級の既得権益を守るためでした。そこでいう「自由民」とは貴族や裕福な商工業者という土地を所有している特権階級をさし、人口の9割を占めている農奴は含まれていません。
国王の行為が法(慣習法)に基づいているかどうかを審査するための機関として作られた「裁判所」(パーリアメント)が後にイギリス議会になっていき、ことごとに王権と対立するようになり、ついには王権を凌ぐ存在になっていったのです。
ところで、憲法は誰が誰に命令しているものでしょうか。反対に言えば憲法に違反するのは誰かと言うことです。上記のとおり、憲法とは王権(国家権力)を縛るためのもので、違反するのも王権(国家権力)です。
ちなみに、刑法、例えば殺人罪の「人を殺したものは死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する」という規定は、被告人に対して法律を適用する裁判官を拘束するものです。
8 議会
議会は、1265年イギリスで開かれ、1302年フランス三部会が召集されました。これらの議会は、「身分制会議」「等族会議」で、貴族、聖職、平民という身分ごとに構成されています。議会が開かれた理由は、王権が議会を開いて租税問題を議論させ、その結果に従って徴税するためのもので、議会に召集された貴族達にとっては、王権による恣意的な徴税を牽制するためです。
9 多数決
ゲルマン社会は何を決めるのも全員一致が原則でした。騎士たちが集まって決議する際には、全員が自分の剣を掲げて喝采することによりました。
多数決が行われるようになったのは、12世紀のローマ教会です。ローマ法王が死んで次期法王を決定する会議「コンクラーベ」で全員一致によりいつまでも決まらないのはよくないという理由から、多数決原理が確立しました。この多数決原理が議会にも適用されるようになり、ヨーロッパの各議会で多数決原理は徐々に取り入れられていきましたが、ポーランドでは18世紀になるまで多数決原理は取り入れられませんでした。多数決原理とは、効率的に物事を決めるための便法として成立したものであり、多数決で決まったことが正しい、ということではありません。単に多数の意見を全体の総意とする、というフィクションに過ぎないのです。
なお多数決原理が定着したのは南北戦争と言われています。
10 民主主義
民主主義とは、議会でもなく、選挙でもなく、多数決でもありません。神の前の平等、法の下の平等思想のことです。
近代民主主義が出現するまで世の中にあったのは、身分であり、特権でした。王権、領主権、ギルド、農奴(家族がバラバラにされない権利)等々
近代民主主義社会は、人間の誰もが「人権」という特権を持つとされるようになったのです。その契機はプロテスタント(=宗教改革)の出現です。プロテスタントは無限で万能の力をもつ絶対的な神の存在を信じることを前提とします。この神の前では、王様であろうと農奴であろうと、誰であろうとすべての人間は同じ(=平等)に見える、すなわち無限大と比較すれば、どんな有限であろうと同視できる、という考え、すなわち人間は全知全能の神の下にあって、みんな平等である、したがって人間が持っている権利もまた同じである、神の前の平等という考え方が民主主義のスタートラインです。
この平等思想が、イギリスにおける清教徒革命(1649年チャールズ1世処刑)やフランス革命(1793年フランス革命ルイ16世処刑)の思想的背景となったのです。
11 ロック思想
中世を終わらせたのはプロテスタントの予定説であり、近代の精神的支柱を作ったのは、「17世紀に身を置きながら18世紀を支配した思想家」(丸山真男)と言われたジョン・ロック(1632〜1704年)です。ロック思想はアメリカ合衆国の独立(1776年)、フランス革命(1789年)に多大な精神的な影響を与えました。
ジョン・ロックは、ピューリタン革命(1641〜1649年)、チャールズ1世処刑(1649年)のさなかに青年期を迎えた思想家です。
ロック思想は、まず「自然人」と「自然状態」を想定します。自然人とは、自由で平等な人間は誰にも束縛されず、自分の意思で行動できる人間を指します。そして、自然人同士は全く対等であり、この自然人同士の関係を自然状態といい、ここでは社会も国家もない世界です。自然人は国家や社会の必要性を感じるようになり、自然人同士が契約を結んで政治権力を作るようになった、すなわち国家は人間相互の契約で作られた(社会契約説)と説いています(1690年 統治二論)。
ロックの時代は、1642年にピューリタン革命が起き、その後1660年にチャールズ2世が王政復古した時代です。王権の濫用を正当化する王権神授説に対する反論として、ロックはそこで「抵抗権」「革命権」という概念、すなわち、「国家権力が暴走した際には1人1人の人間はそれに抵抗することができる。それでもなお暴走を続けるのであれば、革命を起こしてもいい」(伝家の宝刀)を主張しています。
ロックによれば、人間が自分を守ろうとする権利は国家が作られる前からあった「自然権」であるから、市民が武装するのは当たり前ということになります(武装の権利)。
古典派の経済思想もロック思想が根底です。ロックは、労働所有権論「労働は価値を産み出し、所有権は労働によって獲得され、保持される」によって、私有財産の正当性及び絶対性を基礎付けたのです。
なお、民主主義は、本来は、法の下の平等を意味していますが、結果の平等を目指す、すなわち、持てるものから持てない者へ富を分配する共産思想と同視され、有産階級からは嫌悪感を持たれました。社会契約説の信奉者であったアメリカの独立戦争の担い手は自らデモクラートとは言わずにリパブリカンと呼んだのです(アメリカ民主党の発足は1828年)。
また、民主主義は衆愚政治と言われたり(プラトン)、独裁主義の温床になったりすることもあるのです(シーザー、ナポレオン、ヒットラー)。
12 日本国憲法
日本国憲法の前文は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」(社会契約説)を宣言しています。
東大の国際政治学者の石田淳さんは、「安全保障の根幹は国家として大切だと考えるものを守りぬくことで」「その対象には、国民の生命、財産、領土だけではなく、憲法上の価値や理念も含まれる」「(安倍内閣が)安全保障のためとして、憲法をないがしろにしたのは皮肉なことでした。」と述べています。
前記の山口繁元最高裁長官が述べているように、集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持し、従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化してきたのです。もしそれを変えるのなら、憲法改正の必要性を国民にアピールして説得するのが正しいやり方であるように思います。
問い合わせるにはこちら