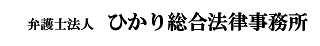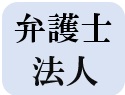建設業法はどう変わったか~中小企業が「適正価格・適正工期」を勝ち取るための交渉術~
2024年から段階的に施行されてきた「第三次・担い手3法(改正建設業法・入契法・品確法)」ですが、2025年12月12日の改正建設業法の施行をもって、いよいよすべての改正法が施行されました。
今回の法改正は、単なる微修正ではなく、建設業界の商慣習を根底から覆すものです。
本コラムでは、新制度のポイントを整理し、中小建設業者が元請企業と対等に渡り合うための「交渉術」について解説いたします。
1 「第三次・担い手3法」が定めた3つのポイント
今回の改正で押さえておくべきポイントは、①労働者の処遇改善、②資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、③長時間労働の抑制(働き方改革)の3つです。
下記で詳しく見ていきましょう。
① 労務費の確保と原価割れ契約の禁止 (建設業法第19条の3)
国(中央建設業審議会)が職種・地域ごとに勧告する「標準労務費」という基準ができました(同法第34条第2項)。
後記(参考)2のポータルサイトから、地域を選んで、職種、区分、工事の種類を選択すると、それぞれの労務費の基準値を調べることができます。
これまでは「安く請け負います」が営業努力とされてきましたが、現在は「標準労務費を著しく下回る見積もりや契約」そのものが法令違反(建設業法違反)となります。
原価割れ契約は許されません。
これは、元請が叩くことを禁じるだけでなく、下請が「安くてもいいから赤字覚悟で仕事を請ける」ことも禁じるという意味で、注文者・受注者双方に義務を課す規制です。
② 「資材高騰リスク」の転嫁ルール化(建設業法第20条の2第2項~4項、第19条第1項8号)
契約締結前に、受注者は、資材供給の著しい減少や資材価格の高騰などの「リスク情報」を注文者に通知することが義務化されました。
そして、実際に資材価格が高騰した際、請負代金や工期をどう変更するかという「スライド条項(変更方法)」を契約書に明記することも義務付けられています。
「その時になったら話し合おう」という曖昧な契約は、もはや許されません。
③ 「著しく短い工期」の禁止(建設業法第19条の5)
働き方改革(時間外労働の上限規制)と連動し、通常必要と認められる工期に比べて「著しく短い期間を工期とする請負契約」の締結が禁止されました。
これも原価割れ契約と同様、ちょっと無理すれば間に合いますから、と言って受注する受注者側(下請)も処罰の対象になり得ます。
2 中小企業(下請)が元請に契約改善を主張する方法
これらを踏まえ、中小企業の経営者や現場責任者は、どのように元請に対して契約内容の改善を主張すべきでしょうか。
ポイントは、「弊社の要望」ではなく「コンプライアンス(法令遵守)」として主張するということです。
① 「標準労務費」を提示して値上げを正当化する
見積もり交渉で「高い」と言われて無理な値下げを要求されたら、国が公表している「標準労務費」を提示してください。
今回の見積もりは、改正建設業法に基づく「標準労務費」を基準に算出しています。
これ以上下げると、弊社としても著しく低い労務費での受注という法令違反になってしまい、お請けできなくなってしまいます、というのが1つの交渉方法です。
このように、「法律を守るために、これ以上は下げられない」という論理で話すことで、感情論を排した価格交渉が可能になります。
② 「リスク通知書」を出して、変更協議の権利を確保する
資材について価格変動のおそれがあるときは、契約前に必ず「資材等の変動リスクに関する通知書」を提出してください。
原油価格高騰による輸送費の上昇や、メーカーからの将来の値上げ通知、震災復興需要による生コンや鋼材の価格高騰などがその例です。
この通知を出しておけば、「契約前にお伝えしましたよね、そうであれば契約変更(スライド条項)の対象になりますから協議させてください」、と言えることになります。
価格変動のおそれがあるときには通知は見積書と一緒に出すのが適切です。
③ 「工期ダンピング禁止」を盾に工程調整を迫る
無理な突貫工事を求められた場合は、「著しく短い工期の禁止」規定を主張します。
その工程ですと週休2日の確保が困難で、改正法の「著しく短い工期」に該当してしまうおそれがあります。
弊社が行政指導を受けるリスクがあるため、適正な工期設定をお願いします、というのが交渉の方法です。
元請企業にとっても、下請に無理をさせて行政処分を受けるリスクは避けたいはずです。「(元請企業である)御社を守るためにも」というスタンスで適正工期を要求することが大切です。
ただ、そうはいってもこれまでの現場のやり方や人間関係があるからなかなか言えません、とか、次の工事で何とかするから今回は泣いてくれと言われています、などというケースもあり得るとは思います。
その際は、うちの弁護士がこうしないと法律上問題だと煩いので・・・と弁護士を盾に使っていただくのも一つの方法です。
契約書の見直しや、元請への通知書の書き方など、具体的な対応に迷われた際は、当事務所にご相談ください。
以上
(参考)
1 国土交通省 第三次・担い手3法ポータルサイト
2 国土交通省 労務費に関する基準ポータルサイト
3 元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン(R8.1最終改訂)
4 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(R8.1最終改訂)
問い合わせるにはこちら