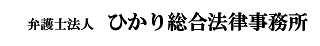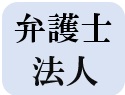定型約款についての実務上の留意点(3)―みなし合意からの除外
前回は、「定型約款該当性の個別的検討」と、「定型約款におけるみなし合意(定型約款の契約への組入れ)」を扱いました。
今回は、「みなし合意からの除外」を扱います。
1 「みなし合意からの除外」とは
民法は、定型取引(定型取引については、「定型約款についての実務上の留意点⑴」を参照してください)を行うことを合意した者が、定型約款に含まれる個別の条項についても合意をしたとみなされる場合(民法548条の2第1項)の例外を定めています。
すなわち、同条第2項は、第1項の条項のうち、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」と規定しています。
これは、548条の2第2項の要件を満たす約款条項は、組入対象の対象外となり、契約内容とならず、結果として法的効力が否定されるという意味です。
ここでの効力否定は、不当な内容の条項はみなし合意規定(同条第1項)から除外されるというもので、契約内容となったうえで、不当性ゆえに無効と判断するという不当条項規制の一般的な枠組みとは異なります。
これまでの裁判例は、民法上の不当条項規制として、公序良俗違反や信義則などの一般条項や契約の解釈によってその契約の内容を規制してきました。
しかし、このような判断枠組みは、条文上は明確ではありません。
そこで、民法は、定型約款規定を創設するとともに、548条の2第2項を設けて、内容規制の明確化を図りました。
この規定によって合意をしなかったものとみなされる条項の例としては、例えば、相手方に対して過大な違約罰を定める条項、定型約款準備者の故意又は重過失による損害賠償責任を免責する旨の条項など、その条項の内容自体に強い不当性が認められるものや、売買契約において本来の目的となっていた商品に加えて想定外の別の商品の購入を義務付ける不当な抱合せ販売条項など、その条項の存在自体を相手方が想定し難く、その説明などもされていないために不当な不意打ち的要素があるものなどが考えられます。
裁判例としては、Yが転売目的を秘して、X会社(インターネットショップ)から転売禁止及び違反した場合の違約金支払条項付きの商品を購入し(送料込みで1万3030円)、他に転売したとして、XがYに対し、違約金(20万円)及び遅延損害金の支払とともに、転売目的を秘して購入したことが詐欺に当たるとして、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、予備的には不当利得返還請求として、金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件転売禁止特約は合意内容となるが、本件違約金条項は、手続の終盤になって初めて表示され、画面上、容易に認識できる状況にはなく、転売禁止商品と表示しても、通常、違約金が課されることを予測できず、加えて、高額の違約金の予想は通常困難であることを踏まえると、同条項は、相手方に一方的に義務を負わせるだけではなく、合理的な予測が困難な不意打ち的な内容であるから、民法548条の2第2項に該当し、合意内容とはならないなどとして、請求をいずれも棄却したもの(東京地判令和5・8・24判例時報2627号36頁)などがあります。
なお、不当性の判断に当たっては、個別具体的な相手方ごとに諸事情が考慮されるため、特定の相手方との関係でのみ合意をしなかったものとみなされるということもありえます。
2 不当性の判断枠組み
(1)信義則による判断
548条の2第2項によりますと、約款条項の不当性は、民法「第1条第2項に規定する基本原則」、すなわち信義則に反して相手方の利益を一方的に害するか否かによって判断することとされています。
(2)不当性の判断要素
548条の2第2項によりますと、民法「第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害する」か否かを判断するに当たっては、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念」が判断要素となります。
(ア)定型取引の態様
考慮要素として、「定型取引の態様」が挙げられているのは、契約の内容を具体的に認識しなくとも定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされるという定型約款の特殊性に鑑みれば、相手方にとって予測し難い条項が置かれている場合には、その内容を容易に知りうる措置を講じなければ、信義則に反することとなる蓋然性が高くなり、この限度で不意打ち条項に果たさせようとしていた機能はなお維持されると考えられるためです。
もっとも、これはその条項自体の当・不当の問題と総合考慮すべき事象であることから、このような観点は一考慮要素として位置づけることとしたものです。
学説では、不意打ち条項規制はいかなる条項が契約内容になるかというレベルの規制であるのに対して、不当条項規制は契約内容となった条項が無効か否かというレベルの規制であるとして、不意打ち条項規制と不当条項規制を区別する考え方も有力です。
この立場は、548条の2第2項は、不意打ち条項規制の拠り所になるものではないと論じています。
しかし、不意打ち条項規制と不当条項規制を区別する考え方に対しては、当事者にとって不意打ちとなるような契約条項は同時に不当条項であると評価される場合が多く、不当条項に該当しない場合であっても説明義務・情報提供義務違反の問題として処理することができるとして、あえて不意打ち条項に関する規定を設ける必要はないとする指摘もあります。
また、個別の相手方の知識や経験によって法的拘束力が左右されると、約款取引の安定性を害するとの指摘や、当該事項に関する契約条項があることが合理的に予測し得なければ常に契約の内容にならないとすると、条項準備者が定型条項を用いて新たな試みや工夫を行うことが困難になり妥当でないとの指摘もあります。
548条の2第2項が不意打ち条項規制と不当条項規制を一本化したのは、これらの指摘を考慮したものです。
(イ)定型取引の実情
「定型取引の実情」を考慮するというのは、上記のような定型取引の一般的な特質だけでなく、その取引がどのような社会的・経済的活動に関して行われるものか、その取引において条項が設けられた理由や背景、その取引においてその条項がどのように位置付けられるものか、例えば、その条項自体は相手方である顧客に負担を課すものであるが、他の条項の存在などによって取引全体ではバランスが取れたものになっているかなどを広く考慮するということです。
考慮すべき諸事情については、従来の一般条項や契約解釈による内容規制において考慮されてきた諸事情も参考になります。
(ウ)取引上の社会通念
当事者間の衡平を図る観点からは、定型取引の態様やその実情のほか、広くその取引において一般的に共有されている常識に照らして判断することが必要になります。そのため、「取引上の社会通念」が考慮要素として明示されています。
3 消費者契約法10条との関係
(1)両規定の相違点
消費者契約法10条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と規定しています。
この規定と民法548条の2第2項の規定は、一見するとよく似ています。しかし、両規定には、次のような違いがあります。
第1に、定型約款に関する規定は消費者と事業者との間の消費者契約に対象を限定していないので、事業者間の取引であっても548条の2第2項は適用される可能性があります。
第2に、消費者契約法10条は、当該条項に対する合意が成立していることを前提として、同条が定める要件を満たす条項を不当条項として無効とするのに対して、民法548条の2第2項は、同項の要件に該当する条項は合意しなかったものとみなしています。
すなわち、548条の2第2項は、当該条項がそもそも契約内容にならないとしている点に大きな違いがあります。
第3に、信義則違反の考慮事情としては、548条の2第2項には「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」という文言が加わっています。
第4に、548条の2第2項と消費者契約法10条とは、その法的介入根拠を異にしています。すなわち、消費者契約法10条は、「消費者と事業者の間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」(同法1条)を前提に、事業者・消費者間の契約条項の内容が、任意法規が定めるデフォルトルールを変更して信義則に反するほどに消費者に一方的に不利になっているかを問い、これが認められれば当該契約条項の効力を否定するというものです。
これに対して、548条の2第2項は、同条第1項により契約内容を具体的に認識しなくとも個別の条項につき合意したものとみなされることに対するバランスをとるために、不当な内容の契約条項を組入れから除外するというものです。
そのため、信義則違反の判断においても、548条の2第2項では顧客である相手方が約款の個別の条項の内容を認識しないまま取引が行われるという定型取引の特質が重視されることになるのに対して、消費者契約法10条においては、消費者と事業者との間に格差があることを踏まえて判断されます。
このように、548条の2第2項と消費者契約法第10条とは、適用範囲を異にするのみならず、その判断において重視すべき考慮要素も異なり、導かれる結論に違いが生ずることもあります。
もっとも、548条の2第2項には、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」という文言が加わっているといっても、消費者契約法10条に関する判例においても契約締結の態様や実情がすでに考慮されており(最判平成23・7・15民集65巻5号2269頁など)、消費者契約については消費者契約法10条と別に民法548条の2第1項が意味を持つ場面はあまり考えられません。
(2)主張の選択可能性
548条の2第2項の規定は、消費者契約法10条の規定と類似していることから、いずれの要件も満たす場合が生じます。
そこで、548条の2第2項が、「…合意をしなかったものとみなす」としていることから、消費者が消費者契約法10条により契約条項の無効を主張したのに対して、事業者側から548条の2第2項により当該条項につき合意がなかったと反論することができるようにも思われます。
しかし、この反論を行うことは、消費者契約法10条の存在意義を否定するものであり、認められません。
上記のように、民法548条の2第2項と消費者契約法10条は趣旨の異なる規定であり、消費者は、両者を選択的に主張することが可能です。
裁判所も548条の2第2項による合意の有無を先行して判断しなければならないというわけではありません。
4 合意をしなかったものとみなされた場合の法律関係
548条の2第2項は、不当条項は1項によるみなし合意から除外されるとする規定です。
したがって、当該条項は、みなし合意から除外され、その効力が否定されることになります。
この場合における法律関係は、解釈に委ねられた問題ですが、ある契約中の一部の条項が無効となった場合の法律関係と同様の問題と位置づけられます。
消費者契約法10条による無効については、ある条項が不当条項に当たる場合に、その条項は全部無効となるとする全部無効説と、無効基準に抵触する限りで無効となるとする一部無効説がありますが、一部無効説に立つと、事業者が包括的な不当条項を定めておいても裁判所がぎりぎり有効な範囲で効力を維持してくれるということになり、不当条項が流布することを防止することができません。
したがって、全部無効説が正当です。
ある条項がみなし合意から除外されると、契約はそれ以外の定型約款の条項により成立したことになります。
ただし、ある条項がみなし合意から除外されることにより契約の本質的な部分に重大な影響を与えるような場合には、例外的に、契約全体が無効となることもありえます。
なお、このコラムの執筆に当たっては、定型約款規定の立法過程の資料を含め、多くの資料を参照していますが、個別的な引用は省略したことをお断りしておきます。
以上
問い合わせるにはこちら