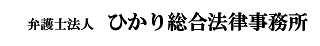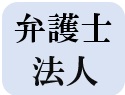地震による建物倒壊と土地工作物責任
令和6年1月1日の能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福を謹んでお祈りするとともに、被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震でも数多くの建物が倒壊しました。
このように、地震などの自然災害により、自己が居住する建物や第三者が所有する建物が倒壊して被害を被った場合、第三者に何らかの責任を問えるのでしょうか。
今回はこの点について考えてみたいと思います。
1 民法が定める土地工作物責任
民法717条第1項は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と定めています。
まず、「土地の工作物」というのは、土地の上に接着して作られた人工的な物を指し、建物をはじめ、塀、石垣、電柱、橋、道路、プール、ゴルフコースなど様々な人工物がこれに該当するものとされています。
そして、近時の裁判例では、土地との接着性は厳格に解すべきではなく、土地を基礎とする設備なども全体として土地の工作物になると解されていますので、エレベーターやエスカレーター、工場内の機械、トイレなどもこれに該当します。
次に、「設置又は保存の瑕疵」とは、工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、瑕疵の内容は、当該工作物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を考慮して具体的個別的に判断すべきものとされています。
そして、責任は一次的には占有者、すなわち工作物を管理して事実上支配する者が負い、例えば建物の賃借人などがこれに当たります。
もっとも占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れますが、その場合でも工作物の所有者は、当該建物を直接管理していなかったとしても、工作物が通常有すべき安全性を備えず、それによって他人に損害が生じた以上、最終的に賠償責任を負担するものとされています。
この所有者の責任は、無過失責任と言われています。
したがって、建物の壁が崩れ落ちたり、塀が倒壊したり、看板が落下したりするなどして、第三者に怪我を負わせた場合などは、一次的にはその建物や塀の占有者、すなわちその建物や塀を管理しているのが賃借人などであればその賃借人が責任を負いますが、賃借人がその建物や塀の倒壊を防ぐために、業者を手配して必要な点検や工事を行っていたなどの事情が認められる場合には、賃借人は責任を負わず、建物や塀の所有者が責任を負います。
但し、業者が不適切な点検や工事を行っていてそのために落下や倒壊が生じたなどの事情がある場合には、第三者に対する損害を負担した占有者や所有者は、その業者に求償できるものとされています(同条第3項)。
なお、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合、設置又は保存に瑕疵がある土地工作物と同様であるとして、第1項が準用されています(同条第2項)。
2 地震による建物倒壊と土地工作物責任
では、地震により建物が倒壊し、当該建物の賃借人や隣家の居住者その他第三者が被害を受けた場合はどうなるでしょうか。
地震などの自然災害は不可抗力ですから、自然災害により建物が倒壊しても、原則として建物の占有者や所有者にその責任があるということにはなりません。
しかし、建物等に瑕疵があり、瑕疵と地震とが競合して建物が倒壊したり、瑕疵により建物倒壊が早まってしまった場合などはどうでしょうか。
この点に関し、平成7年1月17日の阪神・淡路大震災により、賃貸マンションの1階部分が倒壊し、1階部分の賃借人が死亡した事故について、その親が賃貸人である建物所有者を訴えた裁判例があります(神戸地裁平成11年9月20日判決)。
阪神・淡路大震災では、最大震度7の地震により、全壊した建物が10万5千棟にも及びました。
そして、被害が大きかった地域では、老朽化した家屋が多く、また直下型の地震であったことから、比較的新しい建物でも1階が潰れ、その上に2階が落ちるといった被害が非常に多く見受けられました。
上記裁判例のマンションは、昭和39年築の三階建てであり、昭和56年以前のいわゆる旧耐震基準で建てられた建物でした。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されており、それ以降に採用された「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準」であることが求められる新耐震基準に比べて、構造耐力が低い基準です。
しかしながら、裁判所は、建物について、本件建物は設計上壁厚や壁量が不十分であり、それを補う補強方法の妥当性に疑問があり、更に壁に配筋された鉄筋の量が十分でなく、その溶接も不十分であるなどの瑕疵を指摘し、
「結局、本件建物は、建築当時を基準に考えても、建物が通常有すべき安全性を有していなかったものと推認することかできる」
として、本件建物には建築時における設置の瑕疵があったと判断しました。
そして、所有者(賃貸人)の損害賠償責任について、判決は、
「本件建物は、結局は本件地震により倒壊する運命にあったとしても、仮に建築当時の基準により通常有すべき安全性を備えていたとすれば、その倒壊の状況は、壁の倒れる順序・方向、建物倒壊までの時間等の点で本件の実際の倒壊状況と同様であったとまで推認することはできず、実際の施工の不備の点を考慮すると、むしろ大いに異なるものとなっていたと考えるのが自然であって、本件賃借人らの死傷の原因となった、一階部分が完全に押しつぶされる形での倒壊には至らなかった可能性もあり、現に本件建物倒壊によっても本件地震の際に本件建物一階に居た者全員が死亡したわけではないことを併せ考えると、本件賃借人らの死傷は、本件地震という不可抗力によるものとはいえず、本件建物自体の設置の瑕疵と想定外の揺れの本件地震とが、競合してその原因となっているものと認めるのが相当である。」
と判示して、所有者の損害賠償責任を認めました。
もっとも、所有者が賠償すべき損害の額について、判決は、
「本件のように建物の設置の瑕疵と想定外の自然力とが競合して損害発生の原因となっている場合には、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨からすれば、損害賠償額の算定に当たって、右自然力の損害発生への寄与度を割合的に斟酌するのが相当である。そして、右地震の損害発生への寄与度は、前記認定判断にかかる本件建物の設置の瑕疵の内容・程度及び本件地震の規模・被害状況等からすると五割と認めるのが相当である。」
として、建物の瑕疵が損害に対して与えた影響は5割であるとして、賃貸人であった建物の所有者に対し、発生した損害の50%の賠償責任を認めました。
このように、上記裁判例では、建物倒壊の直接の原因が震度7の地震であったとしても、また倒壊した建物が旧耐震基準により建てられた建物であったとしても、建物自体が建築時の基準を満たしていないといえる場合には、建物所有者が賠償義務を負う場合があることを明らかにしました。
また、最終的には地震により倒壊する建物であったとしても、倒壊の順序・方向や倒壊までの時間によっては、結論が異なっていた可能性もあり得たと判示して建物の瑕疵と損害との因果関係を肯定している点、更には、所有者と自然力の損害への寄与度を割合的に斟酌して、所有者の賠償義務を割合的に認めた点などにおいて非常に重要な判断を行っているものと言えます。
したがって、今回の能登半島地震でも地震による建物の倒壊が避けられないものであったとしても、建物が建築当時の耐震基準を満たしていないと言える場合には、建物の占有者や所有者が一定の責任を負担する場合があり得ることになります。
3 終わりに
上記のように自然災害による自然力と土地工作物責任が相互に作用することで被害が生じたといえる場合には、土地工作物の所有者の責任を追及することが可能となります。
地震で倒壊した建物の瑕疵を特定することは非常に難しいことは確かですが、日本にはまだまだ多くの旧耐震の建物が存在することを考えると、今後の同様の被害を未然に防止するためにも、自治体や研究機関が中心となって、できうる限り、建物の倒壊原因を特定することが望まれます。
なお、上記裁判例は、民法717条第1項の「設置の瑕疵」を特定したものですが、同一地域に複数回大きな地震があり、以前の地震で建物に重大な損傷が見られたにもかかわらず、それを長期間放置することによって次の地震で建物が倒壊したなどの事情がある場合や、耐震診断で建物の重大な瑕疵が指摘されていたにもかかわらず、改修工事を行わずに放置していたなどの事情が認められるようなケースでは、土地工作物責任における「保存の瑕疵」が問われる可能性もあり得ると思われます。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
以上
問い合わせるにはこちら