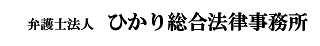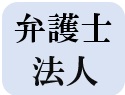「通損補償」(通常生ずる損失の補償)とは何か
令和7年、区分所有法が改正され、賃貸借の終了請求制度が創設された。
マンションの再生(建替え)を行うにあたり、賃借人に通常生ずる損失を補償した上、退去させることができる制度である。
今回は、この改正を契機として、公共用地の取得に伴う損失補償基準(用対連基準)における通損補償について、その意味するところを説明する。
なお、用対連基準は、マンション再生(建替え)だけではなく、通常の立ち退き交渉や再開発の場面でも登場するが、その基本的な考え方は同じである。
1 令和7年区分所有法改正
区分所有法が令和7年に改正され、賃貸借の終了請求、配偶者居住権の消滅請求、及び使用貸借の終了請求の各制度が新設された。
これは、普通借家の場合、借家人は正当事由制度(借地借家法28条)で保護されるから、借家人を退去させた上マンション建替え事業を実施するには当該借家人との間で正当事由を具備した中途解約か合意解約をせざるを得ないが、かかる法規制がマンション建替えの妨げになっていた現状に鑑みて規定されたものである。
賃貸借の終了請求について、区分所有法は、
| 第六十四条の二 建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があつた日から六月を経過することによつて終了する。 3 第一項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。第五項において同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。 4 第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)は、当該専有部分の区分所有者と連帯して前項の債務を弁済する責任を負う。 5 専有部分の賃借人は、第二項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前二項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。 |
と定めた(下線は改正部分)。
即ち、①建替え決議に賛成した各区分所有者(及びその承継人)、②建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(及びその承継人)、③これらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者、又は④賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができ、この請求があった日から6月を経過することで、当該賃貸借は終了するものとされた。
猶予期間が6月とされたのは、借地借家法27条が参考にされたものである。
これは、建替え決議が成立したとしても賃借権が当然に消滅するわけではないという理解を前提としつつ、特定の専有部分につき賃貸借契約がされている場合であっても、他の専有部分の区分所有者はその賃貸借契約について関知し得ないことを踏まえ、区分所有建物を抜本的に再生するために区分所有者間で建替え決議が成立したときは、正当な補償のもとに、賃借権を消滅させることができるとしたものである。[1]
2 通損補償の結論(サマリー)
まず、簡単に結論を述べる。
結論的には、賃借人に支払うべき「通常生ずる損失の補償金」は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(用対連基準)における通損補償と同水準とすることが想定されており(ただし、公共用地の取得の場合との異同を踏まえて算出される必要があるとされている)、簡単にサマリーすると、借家人に支払うべき通損補償は、概ね、
| ①動産移転料 +②借家人補償 {(標準家賃-現在家賃)×2~4年}+{標準家賃×非返還金月数+(標準家賃×返還月数-従前貸主からの返還見込額)×0.2559} +③移転雑費(仲介手数料等) +④営業休止補償(※店舗等の場合) ④-1 年間の固定的経費÷12×1~2か月+ ④-2 従業員の平均賃金の60~100%×1~2か月+ ④-3 年間収益(営業利益+営業外利益-営業外費用)÷12×1~2か月+ ④-4 従前の1か月の売上高×売上減少率(10%~205%)×限界利益率+ ④-5 その他(商品の減損等) |
となる(もちろん事例によって異なる)。
以下、各項目について説明を行う。
3 通損補償の具体的中身
(1)立法過程における議論
当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない(区分所有法63条4項)。
改正における議論の過程では、マンション建替え円滑化法62条に準じて「近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額」とする考え方[2]、通損補償の考え方、区分所有権等の時価の一部とする考え方、借家権価格とする考え方が挙げられていたが、改正法は、このうち通損補償の考え方を採用したことになる。
「通常生ずる損失の補償金」について、要綱案では、「「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)における借家人等が受ける補償(いわゆる通損補償)と同水準とすることを想定しているが、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で、適切な額が算定されることになると考えられる。」という説明がされていた。[3]
公共用地の取得に伴う損失補償基準(及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則)は、一般に「用対連基準」と呼ばれ、公共用地の取得の場面のための基準であるが、民間の立ち退きの場面でも準用されてきたものである。
再開発等、公的な収用の場面では、事業者が公的な資金や補助金を前提に通損補償を行うが、区分所有法が想定するのは民民における区分所有者(賃貸人)による通損補償であるから、両者は場面を異にするのであって、公共用地の取得に伴う損失補償基準をそのまま適用するのはやや合理性に欠けるとも思われる。
この点について、上記したように要綱案には「異同を踏まえた上で、適切な額が算定されることになると考えられる」とあるのだが、改正法の文言にはただ「通常生ずる損失の補償金」とあるし、異同といっても、不随意に賃借権を消滅させるという意味では全く同じであり、主な相違点は主体の経済力である中、文言に「通常生ずる損失の補償金」とある以上、不動産鑑定士は従前どおり公共用地の取得に伴う損失補償基準をベースにして査定せざるを得ないとも考えられる。
以下では、いずれにしても、改正法下でも重要な規範になると思われる公共用地の取得に伴う損失補償基準の説明を行う。
(2)公共用地の取得に伴う損失補償基準(用対連基準)
公共用地の取得に伴う損失補償基準は第4章で「土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償」を定めており、その主な内容は、①動産移転料(公共用地の取得に伴う損失補償基準34条)、②借家人補償(公共用地の取得に伴う損失補償基準34条)、③移転雑費(公共用地の取得に伴う損失補償基準37条)、④営業休止補償(公共用地の取得に伴う損失補償基準44条)等となる(「通損補償」)。
| 通損補償 (主な内容) |
①動産移転料 |
| ②借家人補償 | |
| ③移転雑費 | |
| ④営業休止補償 |
①動産移転料
①動産移転料は、公共用地の取得に伴う損失補償基準において、
| 第31条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い移転する動産に対する補償については、第28条第1項前段に規定する建物等の移転に係る補償の例による。 第28条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地等に建物等(立木を除く。以下この条から第30条まで及び第42条の2において同じ。)で取得せず、又は使用しないものがあるときは、当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとする。 |
と定められているので、動産を通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償することになる。
②借家人補償
②借家人補償は、公共用地の取得に伴う損失補償基準において、
| 第34条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物の全部又は一部を現に賃借りしている者がある場合において、賃借りを継続することが困難となると認められるときは、その者が新たに当該建物に照応する他の建物の全部又は一部を賃借りするために通常要する費用を補償するものとする。 2 前項の場合において、従前の建物の全部又は一部の賃借料が新たに賃借りする建物について通常支払われる賃借料相当額に比し低額であると認められるときは、賃借りの事情を総合的に考慮して適正に算定した額を補償するものとする。 |
と定められ、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則においては、
|
第18 基準第34条(借家人に対する補償)は、次により処理する。 2 本条第1項の補償額は、次の(一)及び(二)に掲げる借家の際に要する一時金の区分に応じて、(一)及び(二)に掲げる式により算定した額を標準として定めるものとする。ただし、当該地域において一時金を支払う慣行のない場合は、補償しないものとする。 (一)賃貸借契約において借家人に返還されないことと約定されている一時金 標準家賃(月額) × 補償月数 標準家賃:従前の借借建物に照応する建物(従前の建物が狭小なため当該地域に照応する建物がないと認められる場合は、当該地域に存在する借家事例を勘案の上、20パーセントの範囲内で借家面積を補正した建物とすることができるものとする。この場合において、借家人が高齢である等の事情があるため生活圏が限定され、当該生活圏外への転居が著しく困難と認められるときは、当該生活圏において従前の居住を継続するのに社会通念上相当と認められる規模の建物(借家面積を40パーセント増加補正した建物を限度とする。)とすることができるものとする。以下同じ。)に基づき、当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる月額賃貸料とする。 補償月数:従前の借借建物に照応する建物の当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる一時金の月数とする。 (二)賃貸借契約において借家人に返還されることと約定されている一時金
(標準家賃(月額) × 補償月数 - 従前貸主からの返還見込額) ×
※標準家賃および補償月数は(一)に定めるとおりとする。
3 本条第2項の補償額は、次式により算定する。 標準家賃 従前の賃借建物に照応する建物の当該地域における新規賃借事例において標準的と認められる月額賃借料とする。 補償年数 別表第5(家賃差補償年数表)の区分による範囲内で定めるものとする。ただし、建物の全部又は一部を現に賃借りしている者が居住又は使用している期間が、この表の区分による年数を下回る場合は、当該期間(当 該期間が1年未満の場合は1年)を年数とみなす。なお、特段の事情があると認められるときは、各区分の補償年数を1年の範囲内で補正することができるものとする。 |
と定められている。
そして、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則別表第5によると、家賃差補償年数は、従前の建物との家賃差が3.0倍超の場合は4年、2.0倍超3.0倍以下の場合は3年、2.0倍以下の場合は2年とされている。
以上を前提に借家人補償(家賃差額補償+一時金保証)について簡単にまとめると以下の計算式になる。
|
借家人補償=
(標準家賃(月)-現在家賃(月))×12×N年
+(標準家賃(月)×非返還金の月数)
+(標準家賃(月)×返還月数―従前貸主からの返還見込額)× |
※N年の部分は、従前の建物との家賃差に応じて、家賃差が2倍以下の場合は2年、2倍超3倍以下の場合は3年、3倍超の場合は4年となる。
※r=年利率、n=賃借期間(通常10年)。
※なおrを3、nを10とすると、は0.2559である。
なお、不動産鑑定評価基準は、「借家権の価格といわれているものには、賃貸人から建物の明渡しの要求を受け、借家人が不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、 賃貸人との関係において個別的な形をとって具体に現れるものがある。
この場合における借家権の鑑定評価額は、当該建物及びその敷地と同程度の代替建物等の賃借の際に必要とされる新規の実際支払賃料と現在の実際支払賃料との差額の一定期間に相当する額に賃料の前払的性格を有する一時金の額等を加えた額並びに自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し、所要の調整を行って得た価格を関連づけて決定するものとする。」としているので(不動産鑑定評価基準「各論」「第1章」「第3節」「Ⅲ」)、上記の借家人補償の計算式において、借家権価格の(少なくとも一部は)補償されると考えることができる。
ただし、細かいことだが、これは「賃料差額の2~4年分の補償」が即ち「借家権価格」とイコールという趣旨ではない。普通借家であれば2~4年といわず(正当事由の具備状況にもよるが)もっと長く建物を利用できるはずだからである。
だからこそ、不動産鑑定評価基準も、賃料差額の補填は「一定期間」について考慮する旨定め、具体的事例に即した幅のある運用が可能となる表現をした上、更に、賃料差額の補填のみで借家権価格を決するとも定めず、自建敷(自用の建物及びその敷地)価格から貸家敷(貸家及びその敷地)価格を控除して得た価格も算出の上、これと関連づけて借家権価格を算出するよう述べているのだと思われる。
③移転雑費
③移転雑費は、公共用地の取得に伴う損失補償基準においては、
| 第37条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物等を移転する場合又は従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等(以下「代替地等」という。)を取得し、若しくは使用する場合において、移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続に要する費用、転居通知費、移転旅費その他の雑費を必要とするときは、通常これらに要する費用を補償するものとする。 2 前項の場合において、当該建物等の所有者、借家人及び配偶者居住権を有する者又は当該代替地等を必要とする者が就業できないときは、第44条、第47条 及び第51条に規定するものを除き、それらの者が就業できないことにより通常生ずる損失を補償するものとする。 |
とされ、その具体的内容は、移転先の選定に要する費用(仲介手数料)、法令上の手続に要する費用(借家人が商業利用していた際の営業許可や商業登記手数料)、転居通知費(借家人が商業利用していた際の宣伝交通費、挨拶状代等)、移転旅費(移転に伴う交通費)、移転に当たり就業できないことに基づく損失(仕事を休んで引っ越しした場合等)となる。
④営業休止補償
④営業休止補償は、公共用地の取得に伴う損失補償基準においては、
| 第44条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。 一 通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額 二 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減) 三 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。) 四 店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額 2 営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは、仮営業所の設置の費用、仮営業であるための収益減(個人営業の場合においては所得減)等並びに前項第3号及び第4号に掲げる額を補償するものとする。 |
とされ、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則においては、
| 第27 基準第44条(営業休止等の補償)は、土地等を取得する場合においては、次により処理する。 1 本条第1項の補償については、次による。 (一) 通常休業を必要とする期間は、別表第4(建物移転工法別補償期間表)による期間に前後の準備期間を加えた期間を標準とし、借家人が移転する場合又は建物の移転が構外再築工法による場合は、その規模、業種設備等の移転期間及び準備期間等を考慮し、2か月の範囲内で相当と認める期間とする。ただし、特殊な工作機械等があり、その移転に相当期間を要する場合は、その実情に応じて定めるものとする。 (二) 固定的な経費の補償は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 一 公租公課 固定資産税、都市計画税、自動車税等を対象として適正に算定した額を補償し、営業収益又は所得に応じて課税される法人税、所得税及び印紙税、登録免許税等は除外する。 二 電気、ガス、水道、電話等の基本料金 電気、ガス、水道、電話等の基本料金は、その使用が継続すると予測されるものは固定的経費とするが、電話については、休業期間が長期にわたる場合で電話局に一時預けることが適当と認められるときは、局預け工事費及び基本料金のうち、回線使用料(基本料)を固定的経費とする。 ただし、休業期間が長い場合であって解約が可能(解約、再契約することで料金体系上不利となる場合を除く。)である場合は固定的経費としない。 三 営業用資産(建物、機械等)の減価償却費及び維持管理費 休業期間中の営業用資産の減価償却相当額及び維持管理費相当額の合計額のうち、その範囲内で適当と認められる額を補償する。 四 借入地地代、借家家賃、機械器具使用料及び借入資本利子 休業期間中に継続して必要となる経費について、営業の内容を調査して適正に算定した額を補償する。 五 従業員のための法定福利費 従業員のための健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料等の社会保険料のうち、雇主の負担となる額を補償する。 六 従業員の福利厚生費 従業員のための厚生施設費等のうち、雇主の負担となる額を補償する。 七 その他の固定経費 従業員及び役員の賞与、同業組合費、火災保険料、宣伝広告費等について適正に算定した額を補償する。 (三) 従業員に対する休業手当相当額は、その休業期間に対応する平均賃金の100分の80を標準として当該平均賃金の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額とする。ただし、次の各号に掲げる場合 には、減額し、又は補償しないものとする。 一 同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従業できるとき。 二 営業所の休止に関係なく、外業に従事できるとき。 三 従業員が一時限りの臨時に雇用されているとき。 四 家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費から除外したとき。 (四) 休業期間中の収益減又は所得減の補償額は、休業期間中、当該営業所により得られる予想収益(又は所得)相当額とする。ただし、セールスマン等により営業の一部を継続できる場合には、それによる予想収益(又は所得)相当額を控除するものとする。 (五) 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額は、次式により算定する。 得意先喪失補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率 売上減少率 別表第8(売上減少率表)による。 限界利益率 個々の営業体の営業実態、営業実績等に基づき次式により算出する。 (固定費+利益)÷売上高 この場合における固定費の認定は、別表第9(費用分解基準一覧表)による。ただし、費用分解基準一覧表を適用して個々の企業ごとに限界利益率を算出することが困難な場合は、「中小企業の財務指標」(中小企業庁編)の「実数分析データ」「中分類」における業種別の損益計算書に掲げる計数を用いて次式により算出することができるものとする。 限界利益率=(売上高-(売上原価-労務費-賃借料-租税公課))÷売上高 |
とされている(なお、営業の継続が不能と認められる場合や、仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当な場合については、別途定めがあるので、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則を確認されたい)。
まず、①固定的な経費の補償は、休業を余儀なくされた場合に、休業期間中も固定的に支払いを要する経費を補償するものである。
「年間の固定的経費÷12×休業期間」という計算式で算定する。
ここで、休業期間を如何に設定するかが問題になるが、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則「第12」は上記のとおり「借家人が移転する場合…その規模、業種設備等の移転期間及び準備期間等を考慮し、2か月の範囲内で相当と認める期間とする。ただし…その移転に相当期間を要する場合は、その実情に応じて定めるものとする。」としているから、1~2か月程度が標準的な休業期間になると思われる。
また、従業員がいる場合は、休業により収入を失う従業員の賃金相当額が加算される。「平均賃金の60~100%×休業期間」という計算式で算定する。
次に、②収益減(個人営業の場合においては所得減)の補償は、休業を余儀なくされた場合に、休業期間中の収益減を補償するものである。
「年間の収益(営業利益+営業外利益-営業外費用)÷12×休業期間」という計算式で算定することになる。
休業期間の定め方については上記と同様である。
③得意先喪失の補償は、休業を余儀なくされた場合に、得意先を喪失し(失注し)減収すると思われることから、それの補償をするものである。
「従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」という計算式で算定する。
売上減少率は公共用地の取得に伴う損失補償基準細則「別表第8(売上減少率表)」に定めがあり、1か月間の売上高を100として、業種、分類、構外移転(店舗の移転)/構内移転(同一敷地内で再築)により、概ね10%~205%の範囲で算定される。
限界利益率は、個々の営業体の営業実態、営業実績等に基づき、「(固定費+利益)÷売上高」という計算式で算定される。
以上から、得意先喪失補償は、概ね、以下の数式で算定されることになる。
| 得意先喪失補償=従前の1か月の売上高×売上減少率(10%~205%)×限界利益率 ※限界利益率=(固定費+利益)÷売上高 |
そのほか、④移転に伴い通常生ずる損失(商品の減損、移転広告費等)があれば、補償の対象になる。
⑤通損補償のまとめ
以上をまとめると、標準的には、
|
借家人に支払うべき通損補償= ①動産移転料 +②借家人補償 {(標準家賃-現在家賃)×2~4年}+{標準家賃×非返還金月数+(標準家賃×返還月数-従前貸主からの返還見込額)×0.2559} +③移転雑費(仲介手数料等) +④営業休止補償(※店舗等の場合) 標準家賃(月額) × 補償月数
④-1 年間の固定的経費÷12×1~2か月+ |
が通損補償の具体的内容ということになる。
ただし、当然のことながら、この計算式は一例であり事例ごとに異なる値があり得るし、用対連基準自体、具体的な場面ごとに解釈の余地がある基準であることは留意の上、妥当な通損補償を査定することが必要である。
以上
[1]「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」74頁。
[2]なお、マンション建替え円滑化法におけるマンション敷地売却制度においては、通損補償の考え方が採用されている。マンション建替え円滑化法143条3項。
[3]法制審議会区分所有法制部会第17回会議(令和6年1月16日開催)部会資料27-2「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)についての補足説明」。
問い合わせるにはこちら