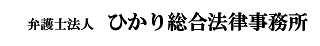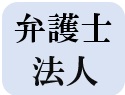定期建物賃貸借契約における事前説明について
1 定期建物賃貸借契約とは
定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」といいます。)とは,当該物件に住むことができる期間が予め決められている,つまり,契約の更新がない賃貸借契約をいいます。貸主と再契約の合意がない限り,借主は,あらかじめ定められた期限が到来すると,当該物件を出ていかなくてはなりません。
貸主がこの定期借家契約を利用するケースとして,例えば,転勤等の理由により持ち家に一時的に住むことができなくなった場合に,その期間に当該物件を貸し出すことで,賃料を得るということが挙げられます。また,リゾート地や地方に所有している別荘やセカンドハウスを,オフシーズンの短期間だけ,定期借家として貸し出すこともあり得るでしょう。
他方で,定期借家契約を利用する借主側のメリットとしては,上記のとおり,定期借家契約の対象となる物件は,分譲マンションや一戸建てなど持ち家であることが多く,より良質な住宅を賃借できる可能性があるということが考えられます。また,借り手がつかないということを避けるために,賃料を相場より下げたり,礼金を不要としたりする定期借家契約も多くあり,このことをメリットと考える方もいるようです。
2 定期借家契約における事前説明の必要性
この定期借家契約を締結する際,普通借家契約と異なる特徴的な法規制があります。すなわち,定期借家契約をしようとするときは「建物の賃貸人は,あらかじめ,建物の賃借人に対し,同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により賃貸借が終了することを,書面を交付して説明しなければならない」のです(借地借家法38条2項)。そして,この「説明をしなかったときは,契約の更新がないこととする旨の定めは,無効」となります(同法同条3項)。
なお,同条2項は,「書面を交付して説明」と規定されていることから,単に書面を交付しただけでは同条の説明義務を尽くしたとは一般的には解されていません(東京地判平成18年1月23日LLI/DB判例秘書登載)。つまり,同条2項の説明義務を尽くしたというためには,書面を交付したうえで,さらに口頭による説明を要するとされているのです。
3 事前説明の有無が争点となった事例
事前説明における「書面」につき,賃貸借契約書と別個に必要か,または,更新がなく,期間満了によって賃貸借契約が終了する旨を記載した契約書を交付することで足りるか否かは,争点として従前から議論がなされてきました。この争点に対し,最高裁は,
「法38条1項の規定に加えて同条2項の規定が置かれた趣旨は,定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って,賃借人になろうとする者に対し,定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを理解させ,当該契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供することのみならず,説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。
以上のような法38条の規定の構造及び趣旨に照らすと,同条2項は,定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って,賃貸人において,契約書とは別個に,定期建物賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上,その旨を説明すべきものとしたことが明らかである。そして,紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると,上記書面の交付を要するか否かについては,当該契約の締結に至る経緯,当該契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といった個別具体的事情を考慮することなく,形式的,画一的に取り扱うのが相当である。
したがって,法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。」(最判平成24年9月13日金融・商事判例1417号8頁)
と判断しました。
定期借家契約は,賃借人保護の観点から,公正証書等書面によって契約をすることが求められていました。それに加え,本件最高裁判決が,契約書とは別個独立の書面の交付を要求したことで,より一層,賃借人を保護する必要があることを示したものと考えられます。
4 今後の課題
もっとも,契約書とは別個独立の書面が具体的にどのようなものである必要があるのかはまだ示されていません。例えば,重要事項説明書を用いて説明した場合の当該説明書は,どのように評価されるのか,判断は分かれるでしょう。
また,説明の程度についても,最高裁による明確な判断は未だになされていません。
定期建物賃貸借は,平成12年3月に導入され,まだまだ解釈に争いがある部分が多く,今後も最高裁の判断に注目すべき分野といえます。
以上
問い合わせるにはこちら