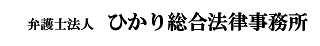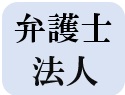withコロナ時代のオフィス賃料(賃料減額請求)
1.はじめに
令和2年2~3月頃から顕在化した新型コロナウィルス感染症の拡大により、我が国の不動産業界は大きな変化を余儀なくされている。
令和2年5月に実施されたCBREの調査によると、銀座、表参道・原宿、新宿、心斎橋などの主要な商業エリアの路面に店舗を構える小売店の9割が、コロナを理由として賃貸人に対し賃料を減らすよう求めたという。[1]
また、多くの企業が在宅ワークを取り入れることでオフィス需要は低下する流れとなり、この流れの中で、パソナグループは淡路島に本社機能を移転すると発表した。[2]
令和元年に平均賃料で千代田区を抜き人気が高かった渋谷区においては、ベンチャー企業が撤退すること等により、空室率が上昇し、平均賃料も下落している。[3]
今後、オフィス需要の低下と連動して、賃料はここ数年間見られた継続的な上昇傾向を脱し、低下傾向に入ると考えられる。
私自身、コロナ禍の中、多くの賃料交渉に関わったのだが、令和2年4月~夏頃までの時点では、賃料減額請求権が行使される事案は少なく、賃貸人・賃借人間における任意の交渉により3~6か月程度の賃料減免を認める方法で双方譲歩したケースが多かったように感じる。
コロナ禍の影響が数値化して顕在化するに従い、借地借家法上の賃料減額請求権が行使されるケースが増えると予想される。この機会に、賃料減額に関する基本知識を確認した上、現時点での見通しや取るべき対策をまとめてみよう。
2.民法上の賃料減額請求
まず、民法上、設けられている賃料減額請求権について確認する。
令和2年4月1日以前の旧民法611条1項は、「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。」と定めていた。
他方、令和2年4月1日施行の新民法611条1項は、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と定めている。
重要な改正点は、「滅失」とあったのが「滅失その他の事由」とされ、一部滅失に限定せず、一部使用不能全般を対象とすることとなった点と、請求を待たず当然に減額されるとなった点である。ただし、旧民法下でも、裁判例上は滅失に限定されておらず、使用収益が不可能になっていれば減額が肯定されていたので、その点で実質的な変化はない。
新民法は令和2年4月1日以降に締結された賃貸借契約にしか適用されないので、コロナ禍による緊急事態宣言中の賃料については、(主に)旧民法611条1項の適用の可否が問題となる。この点について、個人的には否定説を取るが、肯定する考え方もあり、実際、民法611条1項が交渉材料として使用されることは多かった。
今後、民法611条1項の出番は減少し,主に借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求が議論の中心となるはずであるから、本稿ではそちらに重点を置いて説明する。
3.借地借家法上の賃料減額請求
借地借家法32条1項本文は、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と定めている。
ここでは、公租公課の変動、土地・建物の価格の変動その他の経済事情(物価変動、国民所得水準の変動等)、近傍同種の建物賃料との比較により不相当になった場合、賃料増減額請求権が発生すると規定されている。
借地借家法上はややざっくりとした規定ぶりになっているのだが、実際には、より具体化された理論である不動産鑑定評価基準が定める継続賃料についての鑑定評価手法(4種類)に基づき、継続賃料は決定される。
裁判官は訴訟鑑定で提出された不動産鑑定士による鑑定評価書を相当重視して結論を出しているため、賃料減額請求事件について正確な見通しを立てるには、法理論に加え、鑑定理論の理解が必須ということになる。
4.継続賃料に関する鑑定理論
(1)鑑定理論
不動産鑑定評価基準上、継続賃料の鑑定評価基準は、「現行賃料を前提として、契約当事者間で現行賃料を合意しそれを適用した時点(以下「直近合意時点」という。)以降において、公租公課、土地及び建物価格、近隣地域もしくは同一需給圏内の類似地域等における賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等の経緯の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、契約当事者間の公平に留意して決定する」とされている。
具体的な手法として、①差額配分法、②利回り法、③スライド法、④賃貸事例比較法の4つが定められている。
①差額配分法は、対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料又は支払賃料と実際実質賃料又は実際支払賃料との間に発生している差額について、契約の内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して、当該差額のうち賃貸人等に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料又は実際支払賃料に加減して試算賃料を求める手法である。
この手法は、簡単にいえば、新規賃料を求めて、それと現行賃料の差額のうち一定割合を現行賃料に加減する、という手法である。差額のうち現行賃料に加減されるのは、多くの事案において1/2である。
②利回り法は、基礎価格に継続賃料利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法である。
この手法は、不動産の価格と賃料との間に元本・果実の関係が認められることを根拠として、価格から出発して、価格に利回りを乗じることにより、賃料を求める手法である。
③スライド法は、直近合意時点における純賃料に変動率を乗じて得た額に価格時点における必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法である。
この手法は、現行賃料(のうち純賃料)に各種指数や不動産インデックス(賃料指数、市街地価格指数、建物価格指数等)から求めた変動率を乗じることで賃料を求める手法であるが、マクロ的な判断になりやすく、手法の中で重視されることは多くない。
④賃貸事例比較法は、多数の継続賃料の事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るすべての経済的対価をいう。)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって対象不動産の試算賃料を求める手法である。
この手法は実際の事例に着目した実証的な手法なのだが、現実には、継続賃料の事例資料を収集することが困難であるため、適用されない場合も多い。
(2)実際に重視されやすい手法(差額配分法と利回り法)
上記したとおり、4手法あるといっても、実際には、差額配分法と利回り法が重視される傾向にある。差額配分法というのは、新規賃料から出発する手法だから、新規賃料が下落すれば、導き出される継続賃料も下落方向になりやすい。利回り法は、不動産価格から出発する手法だから、価格が下落すれば、果実たる継続賃料も下落方向になる。このように、継続賃料を考えるに当たっては、価格や新規賃料の分析が必須となる。
なお、差額配分法が重視されることと関連するが、継続賃料は、新規賃料の水準には至らないことがほとんどである。この点も、交渉において留意しておく必要がある。
5.市場の分析
(1)地価
令和2年7月1日を価格時点とする都道府県地価調査(基準地価)は、令和元年7月1日との比較であるため大きな下落は考えづらい(令和元年7月から同年末にかけて地価は上昇傾向)。他方、令和3年1月1日を価格時点とする地価公示(公示地価)については、コロナ禍の影響を受け、それなりに下落するはずである。
例えば、令和3年1月1日の公示地価が令和2年1月1日のそれよりも10%下落しているのであれば、それを前提にして鑑定された対象不動産の価格も下落し、更に、その下落した地価を前提にして求めた新規賃料も下落方向になる。結果、差額配分法で求める継続賃料も下落方向になるし、不動産価格が下落する結果、利回り法で求められる継続賃料も下落方向になる。
(2)賃料
三鬼商事株式会社によると、東京ビジネス地区全体の空室率は、令和元年7月時点では1.71%なのだが、令和2年7月時点だと2.77%である。オフィス需要の低下が顕著に表れている。ただし、平均賃料は、令和元年7月時点では21,665円/坪に対し、令和2年7月時点だと23,014円/坪であり、下落していない。
東京ビジネス地区のうち、渋谷区は変化が顕著であり、令和元年7月時点では1.26%に対し、令和2年7月時点だと3.85%と、相当、空室率が上昇している上、更に、平均賃料も、令和元年7月時点では23,862円/坪だったのが、令和2年7月時点では25,048円/坪となり、一年間で比較すると未だ上昇傾向にあるものの、令和2年4月からは連続して下落傾向にある。
上記で見たとおり、コロナ禍の影響は賃料相場に徐々に反映されてきており、この傾向は、今後、益々強まると思われる。
直近のオフィス賃貸市場に関する情報は、三鬼商事株式会社または三幸エステート株式会社のホームページを参照されたい。[4]
6.賃料減額請求に対し、オーナー側の取るべき対応
令和元年2月頃までは、オーナー(賃貸人)側の取るべき行動は、シンプルであった。即ち、地価や賃料は数年にわたり継続的な上昇傾向にあったので、増額請求をすれば良かったのである。
ただ、コロナ禍により、オーナーの取るべき対応は変化した。令和2年8月頃から、各種指標にコロナ禍の影響が顕在化し始めており、令和3年からは、それなりの幅で地価や新規賃料が下落するため、オーナーは賃料減額請求を受ける側になる。
ここでオーナーが取るべき対応は、問題となる事案における直近合意時点がいつなのか、によって変わってくる。
即ち、継続賃料の鑑定評価というのは、上記したとおり直近合意時点と価格時点の比較をするものであるから、直近合意時点における地価や賃料と、賃料減額請求がされた価格時点における地価や賃料を比較して、賃料減額請求がどれだけの幅で認められるのかを検討した上、対応方針を決定すべきなのである。
そして、一つの考慮ファクターとして、直近合意時点から期間が経過していること(相当期間の経過)は、賃料増減額請求権の独立の要件ではないが、一要素ではあるとされ(最判平3・11・29判時1443号52頁)、通常、一度、賃料の改訂の合意がされたのであれば、その時点からある程度の期間を経過しなければ増減額請求権の要件を満たすことはないとされることも、重要である。[5]
以上を踏まえ、例えば、直近合意時点が好景気時であり(現行賃料が比較的高額であり)、訴訟鑑定に持ち込まれた場合、大幅な下落が発生すると予測されるのであれば、オーナーは、交渉段階において、むしろ積極的に小幅な減額に応じるべき(新たな直近合意時点を作るべき)場面もあるだろう。他方で、直近合意時点の現行賃料が低廉であれば、オーナーは交渉段階でむしろ強気に出て減額を拒むべき場面もある。いずれにしても、妥当な和解ラインを判断するには、訴訟鑑定でどの程度の賃料が出るかを適切に予測することが必要となる。
7.テナント側の取るべき対応(賃料減額請求)
テナント(賃借人)側の取るべき対応は簡単で、地価や賃貸市場の変化を適切に見据えつつ賃料減額請求をすることなのだが、注意することは、減額請求をした後、交渉中に、安易に小幅な合意に応じないこと(安易に新たな直近合意時点を作らないこと)だろう。
以上
[1] 日本経済新聞令和2年9月7日記事。
[2] 日本経済新聞令和2年8月31日記事。
[3] 週刊エコノミスト2020年9月1日号。
[4] 三鬼商事株式会社はhttps://www.e-miki.com/を、三幸エステート株式会社はhttps://www.sanko-e.co.jp/を参照されたい。
[5] 渡辺晋『改訂版建物賃貸借』〔大成出版社・2019年〕342~3頁に、一定の期間経過に関する裁判例の分析が掲載されているので、ご参照されたい。
問い合わせるにはこちら