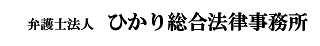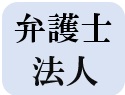1 家事調停における法曹実務家の役割
私は、令和5年2月に弁護士登録をし、同年4月に家事調停委員(以下「調停委員」といいます。)に任命されました。
弁護士としても調停委員としても未だ「若手」ですが、長年、民事及び家事の事件を担当し定年退官前の数年間、主に家事の調停及び審判並びに人事訴訟を担当した元裁判官でもあり、自然と三つ異なる立場からの視点に立ち、事件と相対することが習慣となっています。
そうした、今日の私が改めて強く意識するようになったのは、各当事者が、法的合理性と社会的妥当性を兼ね備えた解決を選択して紛争から解き放たれ、速やかに、一旦止められた時を進めることを手伝うのが法曹実務家の役割であるという理念です。
私は、そのために、調停委員として、
㈠ 当事者の陳述に基づき、
⑴ 双方の主張及びニーズを整理するのと並行して
⑵ 双方の理性(法的規範についての理解、事物に関する合理的理解能力、正義感、公平感、利他的な心等)、相互間の負の感情の質(妬み、 嫉み、恨み、憎しみ、被害者意識)及び程度並びに相互バランスを把握し、
⑶ 冷静かつ丁寧に、時として機転を利かせて、質問又は課題提起を繰り返し、各当事者から、調停委員が中立公平な立場から粘り強く、法的にも社会的にも妥当な解決を目指しているとの一定の信頼を得つつ、双方の理性や良心を強く呼び覚まして、相互の負の感情を和らげる努力をし、
㈡ 裁判官との随時評議に基づき、
⑴ 各当事者から、事実認定に必要な基礎資料を収集し、事実認定につき暫定的心証を共有し、それを前提とする調停委員会による一定の法的評価(これを「評価的調停」といいます。)を下敷きに、
⑵ 各当事者からの信頼と自らの機転をバネにして、相互の主張及びニーズを踏まえた粘り強い利害調整(これを「調整的調停」といいます。)を試み、
㈢ 事件の適切妥当な終了(取下げ、「調停なさず」又は調停の成立若しくは不成立)の十分な地均しをし、
㈣ 調停不成立の場合には、当事者が、調停経過で得られた情報又は成果を、
その後の、審判若しくは人事訴訟又は民事訴訟の審理に資する基礎資料として活用できるようにすることを目指しており、このスタンスに共鳴する調停委員会は少なくありません。
2 今回の呟きの主題
本論考では、上記1の理念の裏返しとして、当事者代理人として、どのように準備し、調停期日に、どのような姿勢で、どのように機転を利かせて依頼人の希望を有効に伝え、調停委員会、反対当事者代理人、更には、反対当事者本人からの信頼を得て、事案の可能な限りの早期解決に繋げることができるのかについて、試論を述べようと考えています。
そのためには、先ず、多くの調停委員会がどのような準備をし、どのような姿勢で調停期日に臨んで傾聴を実践し、担当裁判官とどのように評議して、事案の解決に努めているのかについての概要を知る必要があります。
3 調停委員の準備の概要
㈠ 調停委員会が第1回期日前にすること
⑴ 事案の概要及び争点並びに当事者双方及び各々の背後にいる紛争関係者の間の相互関係の把握
調停委員は、当事者間の紛争の実態を把握するために、
① まず、申立人がいかなる事実関係に基づきどのような権利があると主張し、どのような解決がつけば納得できる(ニーズを満たせる)のかにつき、申立書及びその添付資料から理解できるか否かを把握し、申立人の主張やニーズに不透明性、不合理性又はその客観的説明資料の不足があると思われれば、それらにつき申立人に指示するのではなく、申立人が自らそれらにつき気付けるような臨機応変な質問をできる程度の準備が早期解決の布石になると考えています。
また、答弁書及びその添付資料からは、事実若しくは法的権利の存否についての認識又は紛争解決に必要な双方のニーズの食違いの程度を把握し、相手方の主張やニーズに不透明性、不合理性又は客観的説明資料の不足があると思われれば、それらにつき相手方に指示するのではなく、相手方がそれらにつき自ら気付けるような臨機応変な質問をできる程度の準備が早期解決の布石になると考えています。
② さらに、調停委員会は、事案の複雑度にもよるものの、当事者双方間だけでなく、各々の背後にいる親族関係、親戚関係又は男女関係その他の紛争関係者との関係を正確に理解することが必要であると考えることもあります。
そこで、調停委員会は、そのような場合、申立書及び答弁書並びに各書面添付の基礎資料(戸籍謄本、住民票、事件進行に関する希望聴取書等)及び説明資料等から、事前に当事者双方、各々の親族等その他の紛争の背後にいる関係者を特定して相関図又はメモを作成しています。
そして、調停委員は、直接の当事者だけでなく、各々の関係者の名を正確に記憶することに努め、当事者本人及び代理人弁護士に対し、関係者が当事者間の対立に影響している背景事情を確かめる質問を重ねることが多く、そのようなやりとりを通じて、「当事者双方の主張や提出資料から紛争の実態と背景事情をよく理解しようとしている」とのメッセージを発しつつ、本題に入ること想定している場合が多いのです。
例えば、数次相続を経た末の遺産分割調停や親族間の紛争調整調停では、多数の生存当事者と被相続人又は死亡親族との相互関係の理解なくして、紛争の実態把握及び利害対立の調整をすることができないことは少なくなく、上記のようなやり取りをして初めて、各当事者の主張やニーズを聴取できるようになるでしょう。
③ そうすると、当事者双方の各代理人としては、事前の依頼人との打合せにおいて、まず、各々の主張やニーズが可能な限り合理的かつ透明性があるものになるように、その客観的説明資料を十分に吟味して提出する準備を整えておくことが必要であり、少なくとも、第1回調停期日における調停委員からの質問に対し口頭でも十分に回答できる準備をしておくことが望ましく、そうすることが早期の事案解決のリードに結びつくということができるでしょう。
また、上記②のような場合には、事案の複雑度にもよりますが、当事者双方の各代理人としては、事前に、依頼人から、紛争発生の背景事情を可能な限り広範に聴取しておき、調停委員会からの前記質問に備えて依頼人と綿密な打合せをして、調停期日に、時宜に応じて説明し、依頼人の主張やニーズを正確に伝える準備をしておくことが望ましいということができるでしょう。
⑵ 紛争の実体想定と当事者の主張展開についてのシミュレーション
多くのベテラン調停委員は、上記⑴の①及び②の準備をした上で、多かれ少なかれ、当事者双方に対する質問の順序及び内容、各質問に対する各当事者からの陳述内容の想定、同陳述への想定問答等につきシミュレーションをし、相調停委員、更には担当裁判官との事前評議において、それぞれのシミュレーション結果について意見交換と進行方針の摺り合わせを行った上で、第1回期日に臨むことが肝要であると考えています。
そして、当事者代理人としては、調停委員との質疑応答を通じて、そのシミュレーションや心証形成がどのような方向に向かっているかにつき常にアンテナを伸ばして、進行方針が自らに不利な方向に流れているのではないかという疑問を持ったときに備えて、依頼人の主張やニーズの伝え方を工夫する逆シミュレーションを準備しなければならないでしょう。いわゆる、B、Cプランの準備です。
⑶ 依頼人の主張やニーズの見誤りへの対処
次に、調停委員も人の子である以上、いくら研修やOJTで標準化を図ったとしても、自らの価値観や経験の枠から脱することができずに説明資料からの心証取得の軸がずれ、申立ての適否又はその背後のニーズを見過ごして期日を進行させないとは限りません。
しかしながら、申立代理人としては、そのような局面にB、Cプランを発動できるように事前準備をすることこそ必要でしょう。
㈡ 第1回期日にすべきこと
⑴ 各当事者の主張と主張の背後にあるニーズの把握とその修正
まず、調停は、調停委員が事前のシミュレーションに基づき、各当事者の主張とその背後にあるニーズを把握できれば、円滑に進むことになります。
ところが、調停委員会が想定外の事情に遭遇することは少なくありません。
その場合、調停委員会は、事前のシミュレーションに拘泥することなく、新しく得られた情報を加えて進行方針を速やかに組み替えて行きます。
さもなければ、双方のニーズとかけ離れた進行となるからです。
つまり、事前のシミュレーションと新たに聴取した事情を踏まえて機転を利かせたその修正を繰り返して、評価と調整を兼ね備えた進行をすることが、紛争解決に繋がると考えるのです。
そのためには、調停委員が、以下の配慮や検討をすることが必要と考えられます。
⑵ 事情聴取の実際
① 当事者の一方又は双方に代理人弁護士が就いていない場合には、
a 原則として、同席方式ではなく、交互方式にするのが適切とされます。そして、調停委員会は、その際、
ⅰ 当事者の反対当事者及びその関係者に対する心情に寄り添い、
ⅱ 調停が基礎資料の収集に基づく一定の事実認定及び法的評価と当事者双方の利害を調整しながら、法的合理性及び社会的妥当性のある解決を求めていくもので、そのプロセスに協力して欲しい旨を丁寧に説明するようにしています。
b 次に、代理人弁護士が就任済みの当事者から事情聴取する場合には、調停委員の多くは、本人の同行があっても、基本的には、代理人弁護士から事情聴取をし、それでは不十分な場合に、本人から補足的に事情聴取するという方法が用いられているようです。
調停委員が代理人弁護士の頭越しに当事者本人から事情聴取をすると、代理人弁護士の存在意義を弱めることになり、本人の事情説明能力が不十分な場合には、代理人弁護士が提出した主張書面や説明資料と本人の説明があらぬ齟齬を来して混乱し、無為な時間が経過するおそれがあるからです。
② 以上に対し、当事者双方に代理人弁護士が就任済みの場合には、調停委員会が、同席方式を多用して主張及び説明資料の整理をし、本人の機微に触れる事情の聴取や真のニーズを把握して利害調整をする上で必要な場合に交互方式を活用するようにしているようです。
そうすることにより、当事者本人が代理人弁護士との期日前からの情報共有と信頼関係の維持なくして、円滑な調停の進行がないことを理解し、その認識が作用して、効率的な進行が実現されるからです。
③ 上記①及び②の事情聴取の実際を踏まえれば、当事者代理人としては、当事者本人に自由に発言させるのではなく、事前の打合せでその主張やニーズを事細かに把握して整理し、調停期日において、主に自らが依頼人の主張等を代弁し、調停委員会による法的合理性及び社会的妥当性に適う解決の途に協力することこそ、早期解決という果実を得ることになるでしょう。
⑶ 感情的対立の有無及び程度の把握とその緩和
申立人相互間、申立人本人・相手方代理人間又は相手方本人・申立人代理人間の感情的対立の存否及び程度が、双方の主張及び説明資料の整理の円滑性を左右することは、残念ながら珍しくありません。
そして、これらの感情的対立が、事情聴取を交互にするだけで解消されることはなく、主張及び説明資料の整理の足枷となる事態を招き又は社会的に妥当な当事者間の利害調整の妨げになることもままあります。
そこで、調停委員会は、そのような場合、感情的対立により、各当事者の理性が眠り、相互の不合理な感情が掻き立てられて調停不成立となることのないように、その存否及び程度を把握し、その緩和ケアに努めることを重視しなければならないと考えています。
当事者代理人としては、このような感情的対立が生じたときに、
① 自らも感情的な態度に終始するのか、
② アンタッチャブルになるのか、それとも
③ クールダウンをもたらす積極的な努力をするのか、
運命の分かれ道です。
もちろん、①の態度をとれば、調停は遷延します。
②の態度をとれば、当否に過ぎず、表面上は対立の激化が収まっているように見えますが、マグマに蓋をしているにすぎません。
そうすると、③の努力をするほかはないのですが、その実行には細心の注意と反対当事者に対する真の意味での和解を目指すものでなければならないのは言うまでもありません。
⑷ 家事調停による紛争解決メリットの高低の見立てと進行
① 代理人未就任の当事者は、法律又は家事実務に不案内である場合が殆どですから、弁護士就任済みの当事者に比べると劣勢に立つことが多いのですが、その場合には、前者からの事情聴取を丁寧に行い、法律実務に不案内のために劣勢となることのないような配慮をすることにしています。
そうすると、弁護士未就任の当事者は、家事調停による解決の方が、それに引き続くことのある審判、人訴又は地裁民事訴訟よりもメリットが高いと感じるでしょう。
② 気力、体力又は経済力が相対的に弱い当事者は、紛争の早期解決可能性がある調停に高いメリットを感じるのが常でしょう。
③ 申立ての理由が不合理若しくはそれを裏付ける客観的説明資料が相手方の認否反論を裏付ける客観的資料の質・量を下回る場合の申立人及びその逆の場合である相手方は、審判又は人訴若しくは地裁民事訴訟の判決による一刀両断的な解決よりも、互譲による利害調整が可能な調停に高いメリットを感じるでしょう。
④ そこで、調停委員は、各当事者から得られた資料に基づき、その時点で、各当事者のいずれが調停解決による高いメリットを有しているかについて判断し、場合にもよりますが、その時々の心証を梃子にしてその後の進行を検討するでしょう。
⑤ そうすると、当事者代理人は、その瞬間に垣間見た調停委員会の心証からするとその後にどのような進行となりそうなのかについて、速やかに依頼人に伝えて、上記④の進行に乗るか否かについて真剣に検討する打合せの機会を設けるべきでしょう。
⑸ 期日の連続指定
① 調停委員会は、各当事者の主張及び資料の整理が、早期に完結しない見込みである場合には、一定の進行速度を確保するため、第2回期日指定の調整に加えて、第3回期日の指定の調整をし、各期日のタスクを具体的に示し、その履行を求めるでしょう。
特に、代理人が就任している場合には、期日調整が中々整わない場合が多いので、連続指定が望ましいといえるでしょう。
② そこで、当事者代理人としても、連続指定に乗った方が得策です。
そうすることは、早期解決を願う依頼人の気持ちに寄り添うことになるからです。
4 結語
調停委員会並びに書記官及び調査官は、いずれも、自らの仕事に誇りをもって真摯に取り組み、紛争下にある当事者双方に早期解決による人生のリスタートをもたらすことを期待し、そのために、当事者双方が第1回調停期日前に調停委員会にどのような主張及びニーズ並びにニーズを示しているのか、同期日において、確認しようとします。
そうであればこそ、当事者代理人は、冒頭に、緩慢なプレーをするのではなく、調停委員会の期待に応える濃密なプレーをして、調停の進行をリードすれば、依頼人に最善の利益をもたらさない手はありません。
私の今回の呟きは、守秘義務の壁との関係で、具体例をあまり入れられなかったのですが、いくばくかの示唆になれば幸いです。
以上
問い合わせるにはこちら