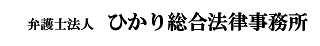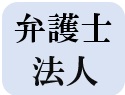遺留分侵害額の請求(相続法改正後)
1 遺留分とは
遺留分とは、相続人が、被相続人の相続財産から法律上取得することが認められている最低限の取得分のことです。
遺留分は、被相続人が遺贈(*)や生前贈与などによって相続財産の大部分を特定の人物に取得させた結果、遺留分を侵害された相続人が生じた場合に意味を持ちます。
遺留分は、相続人が両親・祖父母などの直系尊属のみの場合には、相続財産の3分の1、その他の場合は、相続財産の2分1が保障されています(総体的遺留分)。
但し、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。
2019年7月1日に施行された相続分野に関する改正民法(以下、「改正法」といいます)により、遺留分の範囲や請求の方法などに変更がありましたので、今回は遺留分について触れてみたいと思います。
* 遺贈=遺言によって財産を贈与すること。
2 遺留分算定の基礎となる財産の価額
遺留分を算定するための基礎となる財産の価額は、①「被相続人が相続開始の時において有した財産(積極財産)の価額」に、②「贈与した財産の価額」を加えた額から、③「債務の全額」を控除した額とするのが原則(①+②-③)です(同法1043条1項)。
但し、改正法により、②の遺留分算定の基礎に加えるべき「贈与した財産」の内容が以下の通り一部変更となっています。
ア 被相続人が相続人以外の第三者に対して相続開始前の1年間に贈与した財産(同法1044条1項)
※ 相続人以外の者への贈与の場合は、相続開始前1年間のものに限られています。
イ 被相続人が相続人に対して相続開始前の10年間に、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与した財産(同法1044条3項)
※ 改正前は、相続人に対する贈与は、期間の制限なくすべての贈与が遺留分算定の基礎となる財産に加算されていましたが、上記の通り相続開始前10年間のものに制限されました。
また、遺留分算定の基礎となる財産に加える対象の贈与の価額については、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る」との限定が設けられました(これを特別受益といいます。後記3(2)参照)。
ウ 被相続人と受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って贈与した財産(同法1044条1項但書)
※ 贈与の当時、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った場合には、相続人に対する贈与か相続人以外の者に対する贈与であるかを問わず、また贈与の時期に関係なく、遺留分算定の基礎となる財産に加える必要があります。
エ 負担付贈与がなされた場合には、目的の価額から負担の価額を控除した財産(同法1045条1項)
※ 贈与の中には、例えば、家を贈与する代わりに残りのローンを払うなどの負担付きで贈与することがありますが、このような負担付贈与の場合には、贈与時に残っていたローンの債務などを控除して、贈与価額を算定するということです。
オ 不相当な対価をもってした有償行為(同法1045条2項)
※ 例えば、本来3000万円の価値のある不動産を1000万円で売るなどした場合には、実質的には2000万円の贈与をしたのと同じことになります。
そこで、不相当な対価により有償行為が行われた場合は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行ったものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすことになっています。
上記の例で言うと、当事者双方が悪意の場合には、2000万円を遺留分算定の基礎となる財産に加えるということです。
3 遺留分及び遺留分侵害額の計算
(1)個別の遺留分の計算は、上記により算定された遺留分算定の基礎となる財産に、総体的遺留分割合、更には、法定相続分の割合をかけて算定します。
個別遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産×総体的遺留分×各遺留分権利者の法定相続分
※ 例えば、夫の財産について、妻と子供2人が法定相続人の場合、妻と子はいずれも1/2の総体的遺留分を有しており(上記1参照)、法定相続分は妻が1/2、子供が各1/2×1/2=1/4ですから、遺留分算定の基礎となる財産が3000万円だとすると、妻については3000万円×1/2×1/2=750万円、子らについては、3000万円×1/2×1/4=375万円がそれぞれの個別遺留分額になります。
(2)そして、遺留分侵害額は、個別遺留分額から、遺留分権利者が相続によって実際に得た財産=[相続により取得した積極財産から消極財産(相続債務)を控除して、遺留分権利者が取得した特別受益(*)や遺贈額をプラスしたもの]を控除することにより算出されます(同法1046条2項)。
これを計算式で表すと、
遺留分侵害額=個別遺留分額-〔(積極財産-消極財産)+特別受益+遺贈を受けた金額〕
=個別遺留分額-積極財産+消極財産-特別受益-遺贈を受けた金額
ということになります。
* 特別受益=生前贈与のうち、一部の相続人が被相続人から特別に受けた利益、すなわち、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与をいいます。
遺留分侵害額の算定における特別受益は、相続開始前10年以内の生前贈与のみ認められます。
なお、遺産分割における具体的相続分の算定をする場合の特別受益については、改正法施行前も施行後も、特別受益についての期間制限はありません。
具体的には当職の以前のコラム「遺産分割における問題〜特別受益と持戻し〜」をご参照ください。
4 遺留分侵害額の請求
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者またはその承継人(承継人は、遺留分権利者の相続人が代表例ですが、包括受遺者、相続分の譲受人や、遺留分侵害額請求権の譲受人なども含まれます)は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます(同法第1046条1項)。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
改正法施行前は、遺留分権利者は、遺留分を侵害されたことを理由に、遺留分を超えて遺贈または贈与を受けた受遺者または受贈者(遺留分侵害者)に対して、財産を取り戻す権利を行使することができるものとされており、これは物に対する請求だったため、不動産などは原則として受遺者と遺留分権利者との共有となっていました。
しかし、これでは、持分の処分に支障が生じるという弊害があったため、改正法により、金銭請求(遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求)が認められることとなりました。
これにより、目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の意思を尊重することもできるようになりました。
5 遺留分侵害額請求の行使方法と期間制限
改正法施行後は、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過したときも、請求権は消滅します(同法第1048条)。
したがって、遺留分侵害の事実を知ったときは直ちに遺留分侵害額の請求権を行使する必要がありますが、これは、裁判外で行使してもよく、必ずしも遺留分侵害額を明示する必要はありませんので、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を侵害した相手方に対し、「遺留分侵害額を請求します。」という趣旨の内容証明郵便を送付すれば大丈夫です。
その後に、金銭支払請求として、具体的な遺留分の侵害額を請求するわけですが、「遺留分侵害額を請求します。」という意思表示をした後は、具体的な、金銭債権が発生するので、金銭債権については、債権の消滅時効が適用されます。
すなわち、「権利を行使することができることを知ったとき」から5年で消滅時効にかかります(改正民法第166条1項)。
この「権利を行使することができることを知ったとき」の判断は必ずしも容易ではありませんが、原則として、具体的な侵害額の明示の有無に関わらず、遺留分侵害額請求の行使の意思表示の時から5年で消滅すると考えておいた方が無難です。
なお、遺留分侵害額の具体的な請求は、まず任意の示談交渉を行い、それで解決しなければ調停や訴訟により請求していくことになります。
具体的な請求を行う際は、当事務所にご相談ください。
以上
問い合わせるにはこちら