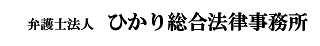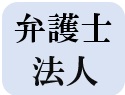相続放棄の熟慮期間について
1 民法第915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と定めています。
このように、相続の承認・放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内にしなければならないことが規定されており、この期間は、一般的に「熟慮期間」といわれています。
そして、相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときは、民法第921条2号により、単純承認をしたものとみなされます。
したがって、熟慮期間が経過してしまった場合には相続放棄はできないこととなってしまいますが、今回は、これが問題となった事案について考えてみたいと思います。
2 事案を簡略化しますと、平成29年に死去した被相続人Aの法定相続人は、Aに先立ち昭和62年に死去していたB(Aの姉)の子らC、D、Eの3名(いずれも高齢)でしたが、3名は、長い間、Aと会ったり連絡を取り合ったりすることがなく、Aの消息を知らず、A死亡の事実も知らずにいたところ、平成31年2月下旬頃に、市役所から「固定資産税の相続人代表者について」という書面を受領し、その内容から、A死亡の事実と、自分達がAの法定相続人にあたることを知るに至ったというものです。
C、D、Eは、相談の結果、相続放棄をすることとしましたが、代表者が相続放棄をすれば足りると誤解していたことから、同じ年(令和元年)の5月18日頃、D1名のみが申述人として記載された相続放棄申述書を家庭裁判所に宛てて郵送しました。
なお、当該申述書は、Dに代わってEが記載したものであり、3人分の申立費用額に相当する収入印紙が添付されていました。
その後、市役所からの上記書面を受領してから3か月以上が経過した同年6月上旬頃、市役所の担当者から、相続放棄は各人が手続きを行う必要があること、固定資産税の滞納があること等の説明を受け、Eは同月19日、Cは同年7月16日、家庭裁判所にそれぞれ相続放棄の申述を行いました。
3 かかるEとCの申述について、前橋家庭裁判所太田支部は、いずれも却下する審判を下しました。
そこで挙げられている理由は、大要、遅くとも市役所からの文書を受領した平成31年2月下旬頃には、相続財産の存在を認識していたと認められるから、熟慮期間もその頃から起算するのが相当である、そうすると、本件申述は、その熟慮期間が既に経過していることは明らかである、というものであり、申述人が誤解をしたことなどは熟慮期間の起算点を後にする理由にはならない、とするものでした。
4 これに対しEとCが抗告したところ、抗告審は、EとCの申述を却下した原審判を取り消し、各申述をいずれも受理する決定を行いました(東京高等裁判所令和元年11月25日決定)。
抗告審は、EらとAの関係、Aの相続を知るに至った経緯や、D1名のみが申述人として記載された相続放棄の申述、その後のEらの相続放棄の申述がなされた各過程につき、詳細な事実認定を行った上で、
「抗告人らが、本件文書(注:市役所からの上記書面)を受領してから3か月以内に相続放棄の申述を行わなかったのは、前記認定のとおり、Dが代表者として申述を行うことによって、相続放棄の手続が完了したと信じていたためであり、そのことは、抗告人Eが相続放棄申述書を代筆した事実や、3人分の収入印紙が添付されていた事実によっても裏付けられている。そして、抗告人らがそのように信じたことについては、軽率な面があったことは否めないものの、抗告人らが高齢であることや法律の専門家でもなかったこと等からすると、強い非難に値するとまでいうことはできないし、抗告人らも相続を放棄するとの認識の下、実際にDの相続放棄の手続が行われた以上、相続財産があることを知りながら漫然と放置していたといった事案と同視することはできない。」
などとし、結論として、
「抗告人らの本件各申述の時期が遅れたのは、自分たちの相続放棄の手続が既に完了したとの誤解や、被相続人の財産についての情報不足に起因しており、抗告人らの年齢や被相続人との従前の関係からして、やむを得ない面があったというべきであるから、このような特別の事情が認められる本件においては、民法915条1項所定の熟慮期間は、相続放棄は各自が手続を行う必要があることや滞納している固定資産税等の具体的な額についての説明を抗告人らが市役所の職員から受けた令和元年6月上旬頃から進行を開始するものと解するのが相当である。」
として、本件各申述はいずれも適法なものとして受理すべきであるとしました。
5 本件では、市役所から受領した書面によって、被相続人が不動産を所有していたこと、それに関する固定資産税が発生していることを認識できたはずですから、原審の判断のように、熟慮期間の起算点を当該書面の受領時と考えてしまいがちであると思われます。
しかしながら、詳細な事実認定から、それが妥当しない理由付けを展開し、原審判を取り消した抗告審の決定は、特殊な事案についてのものとはいえ、形式的な判断で終わらせず実質面をよく考えることの重要性を感じさせるものです。
相続放棄が、他人の債務を承継してしまうことの不都合からの解放として機能することを考えれば、熟慮期間の起算点について画一的ではない抗告審のような扱いがあることは大きな意義を有すると思われます。
このように、相続放棄の熟慮期間が経過してしまったと思われる場合でも、個別の事情によっては申述を行ってみるべきケースがあり得ますので、相続放棄に関してお悩みであれば、まずは弁護士に相談されることをお勧め致します。
以上
問い合わせるにはこちら