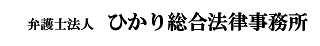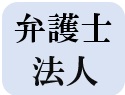高級マンション購入を利用した相続税の節税スキームは使えない?(令和4年4月19日 第三小法廷判決)
1 はじめに
相続税の節税対策として一般的に行われている不動産の購入について、興味深い最高裁判決が出ましたのでご紹介させて頂きます。
不動産購入による節税対策とは、不動産の実際の購入価格と相続税評価額(土地であれば路線価、建物であれば固定資産評価額等を基にした額)の差額分を利用して、相続税の圧縮を図ることを言います。
この時、不動産購入のために高額な借入れを行えば、さらなる相続税の圧縮も可能となります。
特に近年では、高級タワーマンションが乱立し、路線価等と実際の市場価格の乖離が著しく大きい不動産も目立っています。
本判決は、そのような不動産購入を利用した節税スキームが税務署から否認される可能性について示したものとなります。
2 事案の概要
A(被相続人)は、平成24年に94歳で死亡し、上告人らがその財産を相続しました。
Aの相続財産には甲マンション及び乙マンション(以下、合わせて「本件各不動産」という)が含まれていたところ、本件各不動産は、Aが平成21年に信託銀行等から合計約10億円を借り入れたうえで、代金合計約13億8000万円で購入したものでした。
上告人らは、本件各不動産の価額について路線価を基準に合計約3億3000万円(相続税の総額が0円)として相続税の申告をしました。
国税庁長官は、所轄国税局長に対し、本件各不動産の価額につき、財産評価基本通達(以下、「評価通達」という)6項に基づき、評価通達の定める方法(路線価方式)によらずに評価するべしとの指示をしました。
その後、所轄税務署長は、不動産鑑定評価基準により算定した鑑定評価額に基づき、本件各不動産の価額の合計が約12億7000万円(相続税の総額約2億5000万円)であることを前提とする本件各更正処分等をしたため、上告人らが処分の取消しを求めました。
| 購入金額(A) | 申告(B) | 更正処分(C) | 圧縮額①(A-B) | 圧縮額②(C-B) | 甲マンション | 837,000,000円 | 200,041,474円 | 754,000,000円 | 636,958,526円 | 553,958,526円 |
| 乙マンション | 550,000,000円 | 133,664,767円 | 519,000,000円 | 416,335,233円 | 385,335,233円 |
| 合計 | 1,387,000,000円 | 333,706,241円 | 1,273,000,000円 | 1,053,293,759円 | 939,293,759円 |
3 関連法令・通達
(1)相続税法
22条 相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
(2)財産評価基本通達からの抜粋(評価通達)
1項(2) 時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
3項 区分所有に係る財産の各部分の価額は、この通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価する。
6項 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
11項 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
4 裁判所の判断について
本件では、上告人らは国税局が評価通達の一般的な評価方式である路線価方式によらず、不動産鑑定評価額に基づいて不動産を評価したことについて相続税法22条違反及び租税法上の平等原則に反すると主張しました。
(1)相続税法22条違反について
相続税法22条に反するとの主張に対し、本判決は、相続税における時価は客観的な交換価値であるということ及び通達が国民に対し直接の法的効力を有することはない、という従来の判例通説の見解と矛盾しない判断を示しました。
そのうえで、本件では不動産鑑定評価額が客観的な交換価値と認められるため、その価額が評価通達による価額を上回ったとしても相続税法22条に反しないとの見解を示しました。
(2)平等原則違反について
他方、平等原則違反については、評価通達の方法以外による財産評価が相続税法22条に反しないとしても、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の方法による価額を上回る評価をした場合には、「合理的な理由がない限り」、租税法の一般原則である平等原則に反し違反であるとの見解を示したうえで、「合理的な理由」の有無については、相続財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるかどうかで判断するとの基準を示しました。
そのうえで、本件では、評価通達に基づく価額と不動産評価に基づく価額との間に大きな乖離があることを前提に、単にそのことをもって「合理的な理由」があるとは言えないが、さらに、本件各不動産の購入及び借入により相続税負担額が著しく軽減されたという事実や、本件各不動産の購入及び借入行為が、近い将来発生する相続において減税・節税効果があることを知りかつ期待して実行したものであるとして、上告人らの租税負担の軽減の意図を認め、評価通達の方法以外による財産評価に「合理的な理由」があると認定し平等原則違反はないと判断しました。
5 評価通達6項に関する従来の判例及び国税の判断基準
(1)評価通達6項の「著しく不適当」の判断基準について
本判決は、評価通達6項の「著しく不適当」の判断基準について直接言及したものではありません。
しかし、租税法上の平等原則違反か否かの判断は、実質的に評価通達の方法以外による財産評価に「合理的な理由」があるかどうかの判断と共通するものであると考えられますので、「著しく不適当」な場合の判断基準について、従来の国税の考え方をご紹介します。
以下の文章は、税務大学校の論叢(山田重將『財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について-裁判例における「特別の事情」の検討を中心に-』)から抜粋したものとなります。
この論叢の中では従来の判例を参考に評価通達6項の適用について4つの判断基準を示しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/80/02/index.htm
評価通達6項の適用に当たっては、
〔ⅰ〕 評価通達による評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること(評価通達による評価の合理性の欠如)
〔ⅱ〕 他の合理的な時価の評価方法が存在すること(合理的な評価方法の存在)
〔ⅲ〕 評価通達による評価方法に従った価額と他の合理的な時価の評価方法による価額の間に著しい乖離が存在すること(著しい価額の乖離の存在)
〔ⅳ〕 納税者の行為が存在し、当該行為と〔ⅲ〕の「価額の間に著しい乖離が存在すること」との間に関連があること(納税者の行為の存在)
の四つの点が判断基準となると考える。
さらに、この基準の考え方として、
〔ⅰ〕については、不動産の場合、相続開始直前に不動産を取得し、相続税の申告の直後に売却するなど、経済的・一般的合理性が欠如している場合(節税・減税目的であった場合)を指し、
〔ⅱ〕については、不動産鑑定評価や、実際の取引価格が存在すること、
〔ⅲ〕については、「著しい価額の乖離」の有無を判断することとなるが、一律的な基準は確立されておらず、事例ごとに判断を行うこととなること、
〔ⅳ〕については、不動産の場合では、相続開始直前に借入金又は自己資金により不動産を取得し、相続税申告後に売却することなどがこれに該当することが述べられています。
(2)本件における「著しく不適当」な場合の判断基準の適用
本判決でも、上記判断基準を当てはめることは可能であると考えられます。
具体的には、〔ⅰ〕については、本件各不動産の購入がAが亡くなるわずか3年前に行われ、乙マンションについては死後1年以内に売却されていること、Aが購入当時91歳という高齢であったこと、購入資金に占める借入金の額が8割近くを占めていたこと、信託銀行の稟議書に「相続対策」との記載があったこと等が挙げられます。
〔ⅱ〕については、相続の3年前という近時に不動産を購入しており、実際の取得金額が判明していることからも、他の評価方法があったといえます。
また、〔ⅲ〕についても、評価通達に基づく評価額と不動産鑑定評価に基づく評価額との間に約4倍の価格差があることから、「著しい価額の乖離」があったと判断されると考えられます。
〔ⅳ〕についても、Aは相続対策として信託銀行等から借入をしたうえで本件各不動産を購入したことからも、納税者の行為の存在が認められると考えられます。
以上のことから、本判決は、従来の評価通達6項に関する判例及び国税の判断基準と矛盾するものではないと考えられます。
6 おわりに
本判決は、財産の評価に関する従来の判例及び国税の考え方に沿った判断であると言えますが、節税対策として一般的に行われている高層マンション等の購入を利用した相続税の圧縮が、税務署により否認される危険性があることを最高裁が示したという意味で、今後の納税者の節税スキームに影響が出るものと考えられます
もっとも、単に不動産購入を利用した節税スキームがすべて否認される危険があるというものではなく、当面は、本件のような相続開始直前に借入金により不動産を取得し、購入金額の2分の一以下で申告し、相続税申告後に売却するなど、明らかに節税対策としか考えられないような経済的・一般的合理性のない不動産購入のみがその対象となるであろうことをご留意ください。
以上
問い合わせるにはこちら