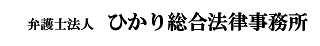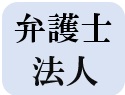音楽教室事業者対JASRAC事件にみる確認訴訟の機能
1.令和3年3月18日知財高裁判決
音楽教室における一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」といいます。)の管理楽曲の利用が、著作権法が定める演奏権(22条)を侵害するか、その成否が争われている事件で、令和3年3月18日、知的財産高等裁判所は原判決を一部変更し、音楽教室における生徒の演奏に演奏権は及ばないと判断しました(教師の演奏については原判決を維持。以下「本判決」といいます。)。
著作法22条は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接・・・聞かせることを目的として・・・演奏する権利を専有する。」と定めているため、権利侵害の成否は、「公衆」「聞かせる」という要件の充足が直接的には問題となりますが、その判断は誰が演奏をしているとみるかによって影響を受けるため、本件でも、音楽教室における管理楽曲の「利用の主体」は誰であるのか、という点が中心的に争われていました。
原判決は、生徒の演奏も音楽事業者が演奏主体であるとした上で、事業者と同視し得る教師が、演奏技術の向上のために生徒自身に(グループレッスンの場合は他の生徒にも)演奏を注意深く聞かせていると認定し、このことから、生徒の演奏は、音楽事業者からみて、公衆である生徒に「聞かせる」目的があるとして、演奏権侵害を認めていました。
2.本判決の特徴(音楽教室における生徒の演奏行為の本質)
本判決は、音楽教室の生徒による演奏行為の本質を、「専ら教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにある」(教授を受ける目的の演奏)と捉えて、この本質を基本軸に生徒による演奏の主体や各要件を評価している点が特徴的です。
この本質を強調すれば、たとえ生徒が教師に指導され、自身の演奏を注意深く聞いていたとしても、そのようにして実践される当該生徒の演奏は、教師に聞かせる目的で行っていること自体に変わりはないため、生徒が公衆と評価されない教師(又はこれと同視し得る音楽事業者)に対して聞かせている構図となり、演奏の主体を生徒と評価しようが、演奏の主体を音楽事業者と評価しようが、当該生徒の演奏に演奏権が及ぶことはない、との結論が導かれることになります。
生徒の音楽教室における演奏の本質を本判決のように専ら教師に向けた演奏として捉えてよいのか、特にグループレッスンでは他の生徒もいるため議論が有るところかと思われますが(この点について本判決は踏み込んだ説明はしていません。)、JASRACも音楽教室事業者である原告ら(以下「原告ら」といいます。)も、上告をしましたので、最高裁においてどのような判断が下されるのか、興味深く待ちたいと思います。
3.原告らの債務不存在確認請求
ところで、本件において、音楽教室事業者である原告らは、JASRACに対し債務不存在確認訴訟という類型の訴訟を提起し、管理楽曲の利用についてJASRACに使用料の請求権が発生しないことの確認を求めています。
いわゆる消極的確認訴訟と呼ばれ、紛争の予防的な意図を持って行われるものですが、確認訴訟は従来予想できなかった新たな社会的紛争を裁判で処理しようとする場合等に多く使用されてきました。
本件でも平成29年2月にJASRACが使用料規程に「音楽教室における演奏等」の項目を新設して平成30年1月1日から使用料徴収を開始する旨を通知し、平成29年6月には文化庁長官に対して変更の届出をしたことで、原告らの法的地位に不安・危険が生じたため、原告らが使用料規程の適用を受けないという権利確認を求めたという流れになります。
ただ、音楽教室による演奏と一口にいっても、楽器演奏と録音物再生に区別され、さらに、演奏は部分演奏、一曲の通し演奏に、録音物は市販CDやマイナスワン音源に区別されます。
また、生徒が1人か複数か、教室は原告ら設営場所か生徒の家か等の違いがあり、原告ら毎に、また、レッスン毎にその演奏の態様が異なることから、原告らは使用料請求権の不存在を求める対象を、態様毎に区別する必要がありました。
原告らの主位的請求をレッスン単位で、種類に応じて整理すると以下のとおりです。
| 録音物の再生 | レッスンの構成員 | 一曲通し演奏 | 対象原告 | 1 | ① | 無し | 教師と10名以下の生徒 | 無し | 全員 | ② | あり | ③ | 教師1、生徒1 | 無し | ④ | あり |
| 2 | ① | あり(市販CD等) | 教師と10名以下の生徒 | 無し | グループA | ② | あり | ③ | 教師1、生徒1 | 無し | ④ | あり |
| 3 | ① | あり(マイナスワン) | 教師と10名以下の生徒 | 無し | グループB | ② | あり | ③ | 教師1、生徒1 | 無し | ④ | あり |
| 4 | ① | 無し | 教師1、生徒1(生徒自宅) | 無し | グループC | ② | あり |