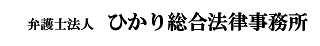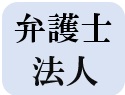米国の当業者における事実認定
特許法第29条2項は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができないと定めています。
この「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことを「当業者」といいますが、この当業者がどのような人物であるのかということについては明確ではなく、当業者の技術水準等を正面から判断する裁判例も見当たりません。
この点、米国では、日本と異なり、当業者の技術水準についての認定が行われ、当該認定をした当業者像を前提に、進歩性(なお、米国では、非自明性という用語が使用されています。)を判断する点が特徴的です。
そこで、今回は、米国における当業者の議論を簡単にご紹介します。
1 当業者概念に関する裁判例
米国における当業者概念は、1851年に、Hotchkiss v. Greenwood事件で、初めて指摘されたと言われています。
長い間標準的に使用されてきた金属や木ではなく、粘土や磁器で作られた新しいタイプのドアノブの特許(特許第2,197号)の有効性につき、「その業務に精通した普通の機械工が持っている以上の創意工夫と技術が要求されない限り、すべての発明の本質的要素を構成する程度の技術と創意工夫が欠如していたことになる。」として、ドアノブを磁器に変えただけの特許は発明者の仕事ではないとして無効と判断しました。
その後、1952年の特許法改正により、非自明性要件が導入され、1966年、Graham v. John Deere事件において、「先行技術の範囲と内容が決定され、先行技術と争点となっているクレームとの相違が確認され、関連技術における通常の技術水準が決定される」という、現在も通用している非自明性の評価基準が示されます。
さらに、1983年、Envtl.Designs, Inc. 対 Union Oil Co.事件において、当業者の通常の技能のレベルを決定する際に考慮され得る要因として、①発明者の教育レベル、②技術分野で遭遇する問題の種類、③これらの問題に対する従来技術の解決策、④イノベーションが起こる速さ、⑤技術の高度化、⑥現場で活躍する労働者の教育レベル、という、マルチファクターテストが示され、当業者の技術水準の認定要素が明確にされました。
その後、当業者概念の広がりによる後知恵バイアスを回避しようとCAFCが採用するTSMテスト(先行技術を組み合わせることの教示や示唆がなければ、当該組合せは自明とはいえないとするもの)により非自明性評価は厳格に行われるようになりますが、2007年、KSR v Teleflex事件において、当業者は、自動機械ではなく、「設計上の必要性又は市場の圧力があり、かつ、特定された予測可能な解決策が限られている場合、通常の技能を有する者は、その技術的な把握の範囲内で既知の選択肢を追求する十分な理由を有する。」、「複数の特許の教示をパズルの断片のように組み合わせることができる。」等と判断し、当業者は、先行技術が明細書で示している特定の課題のみに拘束されることなく、常識を用いて先行技術の組合せを試みることができる柔軟な人物であると判断されるに至っています。
2 当業者認定の例
米国において、当業者は、例えば次のように認定されています。
・「競売市場で取引される譲渡可能金融商品に関する知識を有する者であり、電気工学またはコンピュータ・サイエンスの学士号を有し、かつ、コンピュータおよびコンピュータ・ネットワークに関する約1~2年の実務経験を有する者」と認定。裁判所は争われたクレームの特定の主題に関連する正確な教示を探し出す必要はなく、むしろ、当業者であれば採用するであろう推論や創造的なステップを考慮することができると判断(Papyrus Tech. Corp. v. New York Stock Exch., LLC, 653 F. Supp. 2d 402, 416 (S.D.N.Y. 2009))。
・「ピッチングマシンの設計および製造の仕事においてモーター制御ベンダーを扱う、基本的な工学原理の知識を有する者である」と認定。学位までは不要とすることで、当該人物が、既存のボール投げ機にダイナミックブレーキを組み込むことを考えたと認定することはできないと判断(ProBatter Sports, LLC v. Sports Tutor, Inc., 172 F. Supp. 3d 579, 590 (D. Conn. 2016))。
・子宮アブレーション装置の開発や実装の経験を有する者である必要があるかが問題になった事案において、子宮以外の体腔内の穿孔検出にも適用可能と実施形態が記載されていることを理由に、「教育または実務経験を通じて、生物医学工学、電気工学、機械工学または関連分野の学士号と同等の資格を有し、さらに少なくとも2~3年の電気外科用機器の開発または実装の実務経験を有する者」と認定。当該当業者であれば先行技術を組合せる動機があると判断(Hologic, Inc.764 F. App’x 873, 876 (Fed. Cir. 2019))。
3 当業者の暗黙知を顕在化できるか
このように、米国では、非自明性の評価において、当業者の認定ステップを介在させることで、先行技術の組合せにおける当業者の知識や推論を補強し、具体化する工夫が行われ、当該特許の非自明性判断に係る論理的な説得力を獲得しようとしている点は興味深いところです。
但し、学位や知識レベルの認定と非自明性評価にかかる結論との関係性について、具体的な論理過程にまで言及している例は、多くはないようです。
この点について、当業者概念が、学歴の羅列で構成され、明示的には役に立っていないという研究も存在しているようです(Laura Pedraza-Farina & Ryan Whalen, The Ghost in the Patent System:An Empirical Study of Patent Law’s Elusive “Skilled Artisan”)。
確かに、当業者の知的水準を認定するだけでは、当該先行技術から、当業者が発明課題を読み取ることができたのか、または、当該関連する他の技術を組み合わせようと考えたのかという点について、動機付けの論理を強固に繋ぐことは困難であり、そういう意味では、その業界の当業者が、どのように発明課題を解決してきたのか、技術開発における具体的な課題解決へのアプローチ(いわゆる暗黙知)までも明確にしなければ(マルチファクターテストの③)、当業者の実像により接近した説得力のある判断を行うことは難しいということかもしれません(他方で、このような当業者の暗黙知は、現実には明確な形で顕在化していないことが多いため、結局のところ、非自明性の判断においては、調査によって偶々発見できた先行技術文献の記載内容から推論される技術課題と解決手法しか利用できない場合が多いというのが現実であるようにも思われます。)。
とはいえ、当業者の学位や知識水準であったとしても、当業者が当該学習過程で習得した設計開発手法が暗黙知の構成基盤となり得ることを考えれば、先行技術を組み合わせる際の技術関連性の判断等に影響し、その認定が非自明性の判断に寄与する面があることは否定できませんので、日本の進歩性評価においても米国のアプローチを取り入れ、当業者像をより明確にしていくことは意義があるように思われます。
以上
問い合わせるにはこちら