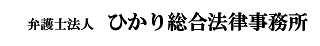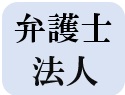タコの滑り台事件と改正意匠法から建築家の本懐を考える
1.中銀カプセルタワーの解体ニュース
銀座にある中銀カプセルタワービルが、2022年中に解体される模様です。
メタボリズム建築運動を牽引した黒川紀章のアイコン的作品であり(1972年竣工)、そのコンセプトは、ユニットであるカプセル型住居の取り替えにより、都市の発展と共に建築物もまた新陳代謝をしながら更新していくというものでした。
しかし、カプセル型住居は一度も取り替えられることなく建物は老朽化し、長らく保存について検討されていましたが、区分所有の現実と有体物の宿命の前に、ついに解体が決定されたということです。
都市の新陳代謝として体現された建築物が、大量生産、大量廃棄社会の前に敗北したかのようなニュースは何とも皮肉ですが、このような、建築家が建築物によって、その精神や生活様式を体現しようとすることについて、私を含め、影響を受けた方は数多いと思います。
おりしも、令和3年12月8日、タコの滑り台事件に関する知財高裁判決(以下「本判決」といいます。)が出て、建築物(応用美術)の創作性について、いわゆる分離可能性説に立ち、タコの滑り台の、美術及び建築物の著作物性が否定され話題を呼びました。
そこで今回は、建築と芸術性の同居(建築の著作物性)について少し考察してみたいと思います。
2.建築の著作物性(創作性)についての考え方
これまで、建築物の著作物性については、応用美術の考え方に従い判断されてきました(大阪高裁平成16年9月29日判決:グルニエ・ダイン事件)。
応用美術とは、美術上の技法や感覚を実用品にも応用したもの等と説明されますが、機能性が重視され、大量生産される実用品に安易に著作権を認めると、意匠法と著作権法の重複領域が増大するため弊害が大きいとして、純粋美術と同視できる美的鑑賞性を有するものについてのみ著作権法上の保護を与える、という考え方がとられてきました(純粋美術同視説)。
建築物も、特に一般住宅のようなものは規格化され、工場内で製造された部材を現場で組み立て量産される側面があることから、これが著作権法上保護されるためには、応用美術と同様に、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となるような建築芸術と呼べるものでなければならないとされてきたのです。
応用美術につき、いかなる基準により純粋美術との同視を評価するかという点については諸説乱立しているところ、実務では、高度の美術性、芸術性を求める従来の立場から、実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となる美的特性を把握しようと、より精緻な評価を試みる立場(分離可能性説:知財高裁平成26年8月26日判決)へと移行しつつある状況になっていると思われます(この点、従来の裁判例の趨勢から離れ、応用美術であっても一般の著作物と同様に著作物性を判断すべきとする立場(美の一体性説:知財高裁平成27年4月14日判決 TRIPP TRAPP事件)が出て議論を巻き起こしましたが、その後この立場に追随する裁判例は出てきておりません。)。
本判決は、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術の著作物として,保護され得ると解する」と述べて分離可能性説に立ちつつ、タコの滑り台のうち、頭部の天蓋部分以外は、滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能や構成から分離できないから、美的鑑賞の対象とならず、唯一分離できる天蓋部分については、タコの頭部形状としてありふれているとしてその創作性を否定しました(また、本判決は、建築の著作物性について、応用美術に係る基準と同様の基準によるのが相当であるとした原審の判断を維持しています。)。
この分離可能性説は、機能や構成を分離する方法や、分離できた部分に対する創作性評価の程度が、他の美術の著作物に比して不明であると指摘されており、私も個人的には、分離の可否に困難を伴うことが想定されることから、上記の美の一体性説のように、作者の個性の発揮による創作性を認めた上でその幅を狭く捉え、類似性評価によって解決を図る方が、実務上利用しやすい感覚を有しています。
3.建築家の職能と本懐
ところで、建築デザインに携わる方々からすれば、冒頭のメタボリズム建築運動の例からも明らかなように、建築物も作り手の思想感情の創作的表現物であることに違いがなく、幼児の落書きにも創作性が認められることに比して、実用品や建築物にのみ厳格な創作性を求められることに、腑に落ちない感情を抱く方は多いようです。
今から100年以上前、日本は明治政府が押し進めた西洋建築の輸入と学習を終え(例:赤坂離宮)、鉄筋コンクリートという自由な造形を可能にする新たな工法を前にして、日本の将来の建築洋式はどうあるべきかとの議論が巻き起こりました。その中で「建築非芸術論」に象徴されるような機能や構造を重視し、意匠を排除すべきとの潮流が生まれ、これに呼応する形で、個人の芸術意欲に基づく「創作」を掲げた分離派建築会運動がおき(建築界で初めて「創作」という言葉が意識的に用いられたと言われています。)、建築固有の課題としての実用や構造と向き合いながら、合理性と科学性、新たな建築様式を追求した近代建築が形作られてきたという歴史があります。
したがって、現代の建築家は、その歴史的文脈からしても、自身の思想感情を建築を通じて体現することをその職業の内に有している側面があります(ちなみに、御茶ノ水駅近くに現存する聖橋は、曲線美(自然式)を追求した分離派建築家山田守(日本武道館や京都タワーを設計)の作品ですが、ヴォイドやパラボラは、力学から派生したものではなく、コンクリートの彫像性を活かしたデザインから発生し、橋の機能や構造とは直接関係がないものであることが知られています。)。
既に大正末期には、かつて工学理論と施工技術を兼ね備えていた建築家は、構造理論の専門家と請負業者の手中に帰し、建築家に残るものは芸術性だけとなったと評され、その職能分化が明らかにされていますが、専門分化が著しく進展した現代の感覚からしても、建築家に期待される芸術的役割は一層高いように思われ、このような大正期からの建築運動と近代建築家の職能分化の流れを踏まえて、改めて応用美術に関する一連の裁判例を見返した場合には、機能や構成と意匠との分離を創作性評価の前提とする考え方には、今もなお、脈々と、実用や構造という課題にかかる建築家の在り方に対する問が横たわっているように思えてなりません。
4.著作権法における保護の限界
ただ、誤解してはならないのは、本判決のような考え方は、一見建築の創作性に対する厳しい眼差しを持っているかのように見えるものの、本質的には著作権法と意匠法との重複適用による弊害を踏まえてなお、当該機能的、実用的制限の下に創作された応用美術に対して、著作権法の保護を認めることができるか、という問題であり、それ以上のものではありません。
著作権法における芸術概念は、著作権法という法概念を前提として捉えざるを得ないのであり、裁判所が実用品や建築物に対する芸術性の多寡や良否自体を評価しているものではない(そもそも裁判所にその役割は果たせないと思われます。)ことには注意しなければならないと思います。
しかし、住宅や商業建築等、大量生産される物品を取り扱う際の建築家の精神性に対し、裁判所が意匠法による保護は別にして、著作権法上の保護の必要性をほとんど感じていないという現実は、「建築各部の定型化が完成せられ、その大量生産が実行せられるようになれば、建築家は、既製部材の適当なる配列と組立とを計算する役を受け持つに過ぎなくなる」という、昭和初期に既に抱かれていた建築家の危機意識がまさに顕在化している状況ともいえ、現代の一般住宅等の設計に携わる建築家は、著作権法上の創作性の発揮という観点において、苦境にあるといってよいのかもしれません。
5.改正意匠法
では、実用的な建築物を取り扱う場合、建築家は、その構造や機能と意匠との関係についていかに向き合い権利を守っていくべきでしょうか。
この点に関し、2020年4月に施行された改正意匠法により、意匠権の対象に建築物や内装(その他、画像も対象追加)が含まれることになったことは、大きな機会と捉えられています。
これまで模倣されても権利侵害を問うことが困難であった業界関係者の関心は高く、改正法施行から1年半で、既に300件以上の登録がなされているようです。
企業のブランド戦略という本来的な目的の他、意匠権は、公報において創作者の氏名が表記されることから、建築家のポートフォリオとすることが可能となります。
また、登録には新規性が要件として必要であるため、登録されているという事実が、当該建築家のオリジナルデザインであることの裏付けとなり、実用的な建築物のデザインに関わる建築家においても新たなモチベーションを付与し、知的生産を高度化する鍵になることが期待されているのです。
6.今後求められる能力
但し、このことは同時に、建築家の業務において、今後は登録意匠の調査能力が求められる時代になることも意味しています。
見たところ、従来の建築手法と思われるような意匠も登録されているため、少なくとも、どのような意匠が登録されているのかを定期的に確認し、その知識を入れておくことは重要です。
万が一、他社の意匠権を侵害し建築や使用差止の対象となれば、その損害は高額になるため、設計過程に調査業務を組み込み、案件によっては予算化することも検討すべきです。
これまで建築家は、創作性が厳格に評価されるが故に、他の建築物を比較的自由に参考にすることができていましたが、今後はメーカーが競合他社の製品の特許を調査するのと同様、自身が設計・提案する意匠と同一又は類似の意匠が既に登録されていないか、事前に確認しておくことが、建築家の業務の一環となる可能性があるのです(しかも、東京地裁令和2年11月30日判決:ワンダーデバイス事件は、使用される時点では不動産として扱われるものであっても、工業的に量産された材料を運搬して現場で組み立て動産的に取り扱うことが可能であれば「物品」に該当するとして、完成した建物に対する組み立て家屋の意匠権侵害を認定したため、調査対象は建築の意匠に限らず広範囲です。)。
このような制度は建築表現の萎縮に繋がるのではないかという指摘もありますが、その積極的な活用によるデザイン競争の利点と合わせて検証しながら制度評価をしていくことになるでしょう(その他、本制度による実務的な影響として、契約時における意匠登録を受ける権利譲渡の取扱い、社内における職務創作の取り扱い、権利出願の際の創作者認定方法等、検討事項が多々ありますがここでは措いておきます。)。
7.さいごに
どのようにデザインを活かし、社会に広め、その本懐を遂げるのか、本判決を含む一連の裁判と改正意匠法を前に、今後は実用的な建築物を取り扱う建築家にも、知的財産法に関する素養が求められる時代がくることが予想されますが、私も弁護士として、より良いサポートができるよう、日々研鑽を積んでいきたいと思います。
以上
問い合わせるにはこちら