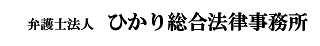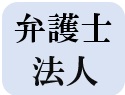特許庁での出向経験を振り返って
1 はじめに
私は、2022年5月~2025年3月まで、特許庁審判部審判課審判企画室に非常勤の審・判決調査員として出向し、約3年間にわたって、弁護士と公務員の二足の草鞋を履く生活をしていました。
今、フルタイムで弁護士として業務に携わる日々に戻ってちょうど約5カ月ですので、出向当時のことを振り返りつつ、出向の経験が今の業務にどのように活きているか、整理してみたいと思います。
2 そもそも、審・判決調査員とは?
2020年度版特許庁行政年次報告書の145頁において、審・判決調査員につき以下のとおり説明されています。
「法曹資格等を有する者を『審・判決調査員』として採用し、口頭審理、審理事項通知書、調書等の内容に関する参考意見の作成と審判官へのフィードバックを、外部的視点を組み込む形で行うことにより、口頭審理の更なる充実を図っている。また、審・判決調査員に対して民事法的側面から審理業務について相談する、審決取消訴訟の判決分析を依頼するなどにより、審理の一層の適正化に取り組んでいる。」
このように、審・判決調査員には、これまでの審判や裁判での経験を踏まえて、口頭審理や審決等の内容をより充実したものにする役割が求められています。
審・判決調査員は、基本的には、弁護士が5名、弁理士が4名の合計9名で構成されており、審判企画室、商標部門、訟務室に配置されそれぞれ執務に当たっています。
私は、訟務室にて約3年間の出向生活を過ごしました。
3 審・判決調査員の業務内容
審・判決調査員の具体的な業務内容としては、
①各部門(特許でいえば、大きく分けて機械分野、電気分野、化学分野があり、その他、商標分野、意匠分野を取り扱う部門があります。)や書記官から来る法律相談の対応(口頭審理や審決取消訴訟等の業務を行う上で不明点があった場合に法律相談が来ます。)
②口頭審理を傍聴し良かった点及び改善点をフィードバックする業務
③審決取消訴訟の判決分析
④審判実務者研究会(産業界、弁理士、弁護士、裁判官及び審判官が審決や判決の研究を行う会)の取りまとめ
⑤審判官向けの研修
⑥審判便覧の改訂支援
⑦特許庁長官が被告となる査定系(拒絶査定不服審判等)の審決取消訴訟において、特許庁として提出する準備書面作成のサポート
などとなります。
官公庁への出向というと、法改正や新法制定に関わる印象が強いかもしれませんが、このポストに関しては、実際に動いている口頭審理や審決取消訴訟において問題となった論点に関する裁判例や文献のリサーチが中心的な業務です(時期によっては、上記の審判便覧の改訂支援などのように制度に関する業務にも携わることができます。)。
口頭審理の進め方、審理事項通知書(口頭審理の前に両当事者に対して通知する書類)に何を記載すべきか、審決の起案、審決取消訴訟(特許庁長官が被告となるいわゆる査定系に関するもの)において特許庁が提出する準備書面の起案などに関して、これまでの審判や裁判での経験を踏まえてアドバイスを行っていました。
特に印象に残っているのは、上記④の実務者研究会への参加です。
企業の知財部の方、弁理士、弁護士、裁判官及び審判官の方々がそれぞれの立場で多岐にわたる意見を述べるこの場は、各参加者の方にとって「なるほど、そのような考え方もあるのか。」と新たな気づきを得ることができる場であり、例年、参加できてよかったとのお声をいただいています。
もちろん、我々、審・判決調査員としても、学びの多い場であり、報告書には記載されないその場限りの忌憚のない議論を聴くことができて刺激的でしたし、その議論の内容を整理して報告書のドラフトを作成することができたのは大変貴重な経験でした。
4 今、出向の経験を踏まえてどのような仕事をしているか?
今は、特許庁への出向を終え、弁護士としてフルタイムで業務に携わっているわけですが、知的財産関係の案件でいうと、特許や実用新案に関する侵害案件や特許出願を含めた特許戦略のコンサルティング業務を多く扱っています。
後者については、どのような範囲で特許を取得していくのか、特許庁の審査をクリアし、また、仮に特許異議の申立てや無効審判請求を受け、その先の審決取消訴訟までもつれた場合であっても無効にさせないためには、どのような技術内容をどのような記載ぶりで書けばよいのかといった点につき、特許庁で審判官の方々と共に仕事をした経験を踏まえてアドバイスをしています。
5 さいごに
出向中、様々な技術、商標、意匠に触れ、改めて知的財産という分野の面白さ、奥深さに気づきました。
私としては、企業や個人が発明した技術や創作したデザイン等が特許、商標、意匠という形でしっかりと保護されれば、さらに発明や創作のモチベーションが上がり、それが社会全体に広がっていけば、ひいては日本全体の技術水準の向上に繋がっていくのではないかと考えています。
そのお力添えができればと考えておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
以上