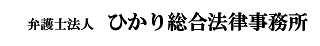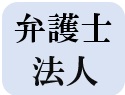知財高判令和4年10月20日(令和2年(ネ)第10024号)について
このコラムでは、令和4年10月20日に判決が出た知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)のいわゆる大合議事件につき解説します。
なお、大合議事件とは、重要な法律上の争点を含み、裁判所の判断が企業の経済活動等に重大な影響を与える事案につき、一定の信頼性のあるルール形成及び高裁レベルでの事実上の判断統一が要請されることから、その要請に応えるために、知財高裁第1部から第4部の裁判長を含む5名の裁判官から構成される合議体により審理及び裁判を行う制度をいいます。
大合議事件の制度は平成16年4月に始まり、この事件で14件目になります。
この事件では、特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、推定が覆滅された部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項を適用することができるかという論点について、知財高裁大合議による判断が下されました。
1. 事案の概要
この事件は、「椅子式マッサージ機」という名称の特許権者である原告が、被告に対して、被告の販売するマッサージチェアが原告の特許権を侵害しているとして、対象となるマッサージチェア(以下「被告製品」といいます。)の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案です。
この事案では、複数の特許権、複数の被告製品が問題となりましたが、このコラムでは、原審である大阪地裁と知財高裁で判断の分かれた特許(判決で本件特許Cと呼ばれているので、ここでは特許Cと呼びます。)と推定覆滅が問題となった被告製品(判決で被告製品1と呼ばれているので、ここでも同様に被告製品1と呼びます。)について取り上げたいと思います。
2. 被告製品1が原告の特許Cを侵害したか?
特許Cに関しては、マッサージチェアの「空洞部」に関する解釈が問題となりました。
特許C記載の発明には、マッサージチェアの肘かけの部分に空間があり、そこに腕を通して腕全体をマッサージする機能が搭載されており、「空洞部」とは、挿入した前腕部を保持するために設けられたものでした。
そして、この「空洞部」について、特許Cの明細書には、「肘掛部の左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面部から形成」などと記載されていたことから、「空洞部」の全体に立上り壁が存在しなければならないかという点が問題となったのです。
原審である大阪地裁では、「空洞部」が外側立上り壁、内側立上り壁及び底面部から形成されるという特許請求の範囲の記載、マッサージの効率性という特許Cの技術的意義からすれば、広範囲を同時にマッサージすることができるように全体にわたって内側立上り壁が存在することが想定されていること、原告の出願経過等を考慮し、特許Cにおける「空洞部」とは全体にわたって内側立上り壁を備えるものであると解釈されました。
他方、被告製品1は、その一部にしか内側立上り壁が存在しないため、非侵害とされました。
これに対し、知財高裁は、特許請求の範囲や明細書には、「空洞部」を形成する内側立上り壁が空洞部の長さ方向全域に設けられる必要があることを規定した記載はないこと、かえって、明細書には、長さ方向全域に左右一対の立上り壁を設けた従来の椅子式マッサージ機には、利用者の肘関節付近を圧迫して利用者に不快感を与えたり、腕を抜く際に妨げになるなどの欠点が開示されていること(特許Cの明細書には、この欠点を解消することが目的の発明であるという記載がありました。)などからすれば、長さ方向全体ではなく、その一部に内側立上り壁が存在するものでも「空洞部」に該当すると解釈し、一部にしか内側立上り壁が存在しない被告製品1も特許Cを侵害すると判示されました。
3. 損害論について
冒頭に記載したとおり、この事件で注目された点は、特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、その推定が覆滅された部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項を適用することができるかという論点です。
結論としては、知財高裁は、これを肯定しました。
この事件では、被告は、①特許Cが被告製品1の部分のみに実施されていること、②市場における競合品の存在、③市場の非同一性、④被告の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、⑤被告製品1の性能(機能、デザイン等)を推定覆滅事情として主張していました。
ですので、知財高裁は、まず、これらが推定覆滅事情として認定できるかを検討しました。
結論としては、この事件で提出された証拠関係からすると、①、③は推定覆滅事情として認め、②、④、⑤は推定覆滅事情として認めないという判断となりました。
次に、知財高裁は、推定覆滅事情として認めた①、③に関して、覆滅された部分について、特許権者が実施許諾することができたといえ特許法102条3項を適用することができるかを検討しました。
結論としては、①については、そもそも、推定が覆滅される理由が特許Cが被告製品1の一部にしか実施されていないという点にあるため、特許Cが実施されていない、つまり、寄与していない部分については、原告が実施許諾できたものではないとして、同項を適用することはできないと判断しました。
③については、市場の非同一性の具体的な内容が、被告製品1がとある国へ輸出されていたのに対して、原告の製品はその国に輸出されておらず、その国の市場において競合関係がなかったという点であったところ、原告自身が輸出していないとしても、被告に対して実施許諾をすること自体はできたので、同項を適用することができると判断しました。
4. 評価
これまで、特許法102条2項において、推定が覆滅された部分に対して同条3項を適用できるかという論点については、学説も両説あり、裁判例の判断も割れている状況でした。
そのような中、知財高裁は、大合議判決というかたちで、これを肯定しましたので、少なくとも、今後、知財高裁としては、最高裁に否定されるなどの事情がない限りは、肯定説に沿って判断するものと考えられます。
これまでの裁判例では、推定覆滅に関する判断は総合考慮で行われており、様々な事情を考慮した上で推定覆滅率は○%と判断されてきましたが、この大合議判決が出たことによって、①そもそも推定覆滅事情として何が認定できるか、②推定覆滅率は何%か、③①で認定した推定覆滅事情のうち、特許権者が実施許諾することができたものは何か、④③で認定した推定覆滅事情にかけるべき実施料率は何%かという手順で判断することになるので、これまでよりも、より詳細に判決上に推定覆滅に関する判断を記載することになると考えられます。
以上