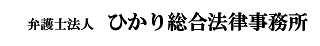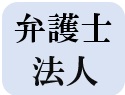アメリカ合衆国内において、死刑を宣告され、その後、無実が判明した人は、何人いるか?
1 182人
「アメリカにおいて、1973年以降、8700人以上の人が死刑を宣告された。そのうち、1500人以上が処刑された。死刑執行待ちの人のうち182人が、冤罪が判明し、社会復帰した。」
ナショナル・ジオグラフィック英語版2021年3月号に掲載されたフィリップ・モリス記者の記事の冒頭である。
この182人という数字は、衝撃的である。
これは、日本語版にも掲載されているようだが、話題になったという話は聞かないようだ。
時機遅れの感はするが、死刑及び誤判の問題に参考となり得るので、誤判・冤罪の点になるべく焦点をあてて、簡単に、そこに示された統計などの紹介を試みたい。
以下は、英語版に基づくが、適宜、筆者のコメントなどを交える。
2 死刑の合憲性
アメリカ連邦最高裁は、1972年のファーマン判決で、州の当時の死刑につき違憲としたことにより、死刑の執行が事実上凍結された。
しかし、1976年7月のグレッグ判決が、条件付きで死刑を合憲とした。
これにより、死刑の執行が再開されるに至った。
先ほどの統計が1973年を始期とするのは、このような理由による。
3 冤罪者182人の内訳
黒人 94人
白人 69人
ラテン系 17人
アジア系 1人
アメリカ先住民 1人
女性は2人。
ともに子殺しである。(なお、嬰児殺で死刑というのは、日本の感覚では考えられないが)
4 死刑宣告から冤罪が判明するまでの期間
1年〜5年 61人
6年〜10年 39人
11年〜15年 30人
16年〜20年 22人
20年以上 30人
最長は43年。
平均はほぼ12年。
なお、わが国では、再審無罪の場合を冤罪として捉えがちかもしれないが、この統計は、通常の上訴審で救済された場合を含む。
そのため、1年〜5年が61人と比較的多いのも、理解できる。
また、総数が182人というのも、その意味で理解すべきであろう。
5 冤罪が生まれた理由(本記事では、無実となった人に個別インタビューするなどして個別事例の紹介もされている。そこで明らかとなっている、具体的事例をも付記する)
(1) 捜査官の不正行為 68%(3件に2件の割合となる)
・無罪を証明し得る証拠の隠匿の例(例えば、犯罪現場の血痕が被告人のそれと一致しない事実をすぐに開示しなかった例)。
・警察官が取引をして、被告人が犯人である旨の証言をさせた例。
・被告人が犯人であるとの証言を撤回しようとしたのに、両親を逮捕するなどと述べて、撤回させなかった例。
・検察官が陪審に偏見を与えた例。
(2) 嘘の被害申告や証人の偽証 62%(これも高い割合である)
(3) 法医学的証拠の誤り 29%
・咬傷が被告人の前歯と一致するとの鑑定が後に誤りとされた例。
(4) 不適切な弁護活動 25%(4件のうち1件の割合)
・刑事事件や死刑事件に経験のない(あるいはほとんどない)弁護士が、被告人に法廷で供述の機会を与えなかったり、被告人のための証人請求を全くしなかった例。
(5) 犯人同一性証言の誤り 19%
(6) 虚偽の自白 13%
・自白を強制し、眠らせずに自白させた例。
子殺しの事件では、弁護人立会なしの取調べで、暴行を認める自白をさせた。
6 無実証明にDNA試験が果たす役割
1989年に、DNA 試験の重要性が認識された。
そして、1993年に、初めて、DNA試験が根拠となって、死刑事件の冤罪が判明した。
その後、さらに26人が、DNA試験のお陰で死刑待ちから解放された。
DNA試験により、真犯人が判明した事例もある。
なお、この1989年を起点として、2020年12月までに、死刑宣告事件に限らず、全体で、2700人以上が、DNA試験によって、無実となった。
7 アメリカの死刑制度の現状
アメリカにおいては、現在、22州が死刑を廃止し、28州と連邦において、死刑が残されている。
しかし、本記事において紹介されている、死刑から生還した人達が参加して、死刑廃止のためなどに活動するWitness to Innocence という非営利団体、及び、その他の団体などの活動も影響し、1996年には国民の78%が死刑を支持していたが、2018年には、支持は、54%に低下している。
1976年の死刑合憲の最高裁判決に加えて、1980年代の法と秩序のキャンペーンが処罰の厳格化の動きに火を付けたことから、死刑宣告数は、1990年に、350件に達していたが、2016年以降は、50件を下回っている。
8 コメント
死刑、冤罪という重大かつ深刻な問題について、ここで、簡単に結論めいたことを述べることは容易ではない。
しかし、この記事に示された統計を基礎に、2点だけコメントしておきたい。
第一は、182人をどう見るか、である。
ある者は、「私は、州によって拉致された」と表現し、ある者は、「私に起きたことは、あなたにも起きることなのだ」と警告する。
陪審制を採用すれば、冤罪はなくなるという、ナイーブな議論が通用しないこと、これが、数値によって、明確に示されている、と見ることもできよう。
第二に指摘したいのは、上記の冤罪の理由が示すとおり、重要なのは、制度を運用する人の問題である、ということである。
これは、裁判制度を問わない。この記事が示す冤罪の理由は、日本においても、大いに参考となる。
「(1)捜査官の不正行為」は、冤罪の大きな部分を占める。
「(4)不適切な弁護活動」を除くその余の4つの理由においても、捜査官の介入などがある場合がある。
捜査官の不正行為を防止するシステムを作ること、そして、現にそれが行われた場合、その事実を弁護人がどうやって立証できるか、が問題となる。
ここに、弁護人が適切な活動を行うことの重要性がある。
不十分な弁護活動などは論外である。
弁護活動を充実させる枠組み作りのため、近年、弁護士会による様々な取組みがなされてきたことは、評価できる。
しかし、個々の事件における個々の弁護士の活動が最後の砦となること、これを忘れてはならない。
初めの裁判が誤ったときのコストは大きい。
本記事は、182人が誤って有罪とされ、死刑待ちで拘禁されていた期間は、合計すると2133年になると、恐るべき数字を掲げる。
最後になったが、本記事には、ナショジオ誌らしく、カメラマン、マーティン・ショーラーによる死刑執行待ち拘禁から解放された人々のポートレート写真などが合計15人分掲載されている。
家族と共に撮影されたものもある。
一人だけでカメラを見つめるものもある。
動画ではないゆえに、静かに訴えかけてくる。
カメラマンの眼は、あくまでも優しい。
刑事事件の弁護人も、かくありたい、と気付かせてくれる。
以上