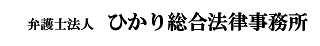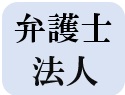袴田事件における3点のねつ造証拠 ―「本件紙幣等」に焦点を当てて―
1 2024年9月26日に、袴田事件(昭和41年6月30日発生)について再審無罪判決が言い渡された。
控訴の申立てはなされず、この判決は確定した。
2 再審無罪判決は、捜査機関によるねつ造証拠3点を指摘した。
- 検察官に対する自白調書(昭和41年9月9日付)のねつ造。
- みそタンクから発見された「5点の衣類」のねつ造。
昭和42年8月31日、従業員が発見したが、それ以前の近い時期に捜査機関によって、タンク内に入れられたと認定。 - 袴田氏の実家から押収された「端切れ」(「5点の衣類」のうちのズボンの共布」)のねつ造。
昭和42年9月12日に押収されているが、そのときまでに捜査機関によって実家に持ち込まれたと認定。
3 本稿では、基本的に、物的証拠に絞って検討する。
物的証拠でねつ造が疑われる証拠として、他に「本件紙幣等」がある。
再審無罪判決は、「本件紙幣等」につき、ねつ造までは認定せず、ねつ造が強く疑われるにとどめている。
結局、ねつ造と認定できるないし疑われる物的証拠は、上記(2)(3)に「本件紙幣等」を加え、合計3点となる。
4 本稿の結論は、「本件紙幣等」は、他の2点のねつ造証拠同様、捜査機関によるねつ造証拠と認められる、である。
(1) まず、「本件紙幣等」について説明する。
昭和41年9月13日(集配は同月11日から12日)、清水郵便局において、「シミズケイサツショ」宛の封筒が事故郵便物として発見され(切手が貼られていない)、在中物として便箋1枚(「ミソコウバノボクノカバンノナカニシラズニアツタツミトウナ」と書かれていた)、紙幣18枚(合計金額5万0700円)があった。うち千円札2枚には「イワオ」と書き入れがある。
(2) ねつ造が疑われる不審な事情は次のとおり。
(あ)紙幣18枚全部、左上と右下の記号番号部分が焼失しており、由来を追跡することができない。
さらに、なぜか、上記のとおり「イワオ」と記載のある紙幣が2枚ある(藤原聡『姉と弟』岩波書店、2024年、43頁に千円札の写真が掲載されている)。
(い)同年9月6日付けの警察官調書及び同月9日(起訴の日)付けの検察官調書に、強取した現金のうち5万円を知人女性に預けたとの自白がある。
上記集配の日との近接性に注意。
(う)筆跡鑑定の結果から、確定第1審判決は、便箋及び紙幣上の文字の筆跡は知人女性のものとした。
しかし、確定控訴審判決は、筆跡鑑定に若干の疑問を指摘し、それだけから差出人が知人女性と断定できないと後退している。
(え)知人女性は、確定第1審で証言したが、「忘れた」「知らない」に終始した。
なお、知人女性は、9月14日(「本件紙幣等」発見の翌日)恐喝の疑いで逮捕され(いわゆる別件逮捕の疑いがあろう)、次いで、贓物寄蔵の疑いで再逮捕されて、同月27日に釈放されたところ(前同書44頁)、その際の供述でも、検察の構図である、紙幣を被告人から預かって発送した旨の供述は全くしていない。
(3) ここで、筆者が過去に研究した「偶然の一致排除理論(coincidence reasoning)」を、本件に適用してみる。
偶然の一致排除理論とは、英米法において、類似事実証拠を有罪の事実認定に利用する場合の一つの理由付けである。
その理解のために、偶然の一致排除理論による理由付けが適切と言われるイギリスのスミス判決(1916年)を例に取り上げる。
「浴槽の花嫁事件」として有名である。
スミスは、結婚したばかりの花嫁を自宅の浴槽で溺死させたという謀殺罪で起訴された。
この事件では、起訴された事件の後も、スミスと結婚した花嫁2人が、いずれも、浴槽で溺死した事実が類似事実として許容された。
同一の男性の3人の花嫁が相次いで事故として浴槽で溺死するような偶然の一致があるだろうか?
いや、そのような偶然の一致はあり得ないから、溺死は謀殺によるものであるという理由付けである。
健全な社会常識に基づく理由付けと言えよう(詳細は、拙著『悪性格と有罪推認―イギリス控訴院判例の分析―』信山社、2019年、86頁以下参照)。
(4) 本件において、ねつ造が強く疑われる物的証拠は3点であり、これを時系列で並べると、
(1)「本件紙幣等」
(2)「5点の衣類」
(3)「端切れ(共布)」
である。
(2)と(3)は、セットになっている(村山再審開始決定は、そう述べている)。
再審無罪判決は、(2)と(3)につき、明白に捜査機関によるねつ造を認定しているが、仮に、いずれも、ねつ造が強く疑われる証拠であるとの前提に立ったとしても、そのように、被告人と事件の結び付きに関し、重要かつ決定的な、ねつ造の疑いがある物的証拠が3点も存在するということは、単なる偶然の一致であろうか?
いや、そのようなことはあり得ない。
そうすると、結局、3点の証拠とも、確定的にねつ造と認定すべきものである。
「偶然の一致排除理論」を適用すれば、こういう理由付けになる。
(5) 次に、「本件紙幣等」のねつ造の順序(時間的経過)を分析してみよう。
本件紙幣を知人女性に預けたとの自白調書を作成し(警察官調書が昭和41年9月6日、検察官調書が同月9日。この検察官調書自体、再審無罪判決が認めるとおり、実質的にねつ造である)、これに沿う「本件紙幣等」をねつ造し、発送し(同月11日ないし12日)(切手を貼らないで、郵便局内で発見されるように仕向けたものであろう)、同月13日、郵便局内で発見され、その翌日の同月14日、知人女性を逮捕し身柄拘束を続け、取り調べしたものの(同月27日までの長期間にわたる)、捜査官の構図に沿う実質的な供述は全く得られず、本件公判開始後、第12回公判(手持ちの資料からは日時を指摘できない。
第16回公判が昭和42年9月5日である)で同女を証人として調べたが、「忘れた」「知らない」に終始した。
知人女性の「本件紙幣等」に関する意味のある供述が得られないため、このねつ造は失敗したと、捜査機関は考えたものと考えられる。
しかしながら、知人女性の供述が得られないにもかかわらず、確定第1審判決及び確定控訴審判決とも、前記の9月9日付け検察官調書を併せて、検察の構図どおりの事実を認定した(確定控訴審判決は、その可能性は極めて強いに後退しているが)。
したがって、知人女性から、ねつ造を裏付ける証言が全く得られなかった第12回公判終了後、「本件紙幣等」に代わる、本件と被告人を結び付ける物的証拠を提出する必要に迫られ、捜査機関は、「5点の衣類」と「端切れ」のねつ造の計画に着手したとみるのが自然である。
この2点のねつ造証拠については、再審無罪判決に詳しいので、ここでは論じない。
「本件紙幣等」につき、若干、敷衍したい。
(6) 「本件紙幣等」には、
(あ)紙幣の記号番号の部分が焼失していること
(い)便箋に記載された文章は、知人女性が書いたとするには不自然な内容であること
(う)紙幣自体に「イワオ」と書き入れがあることは趣旨不明であること
など、不審な点が多々あり、まさに荒唐無稽の証拠と言って差し支えない。
「本件紙幣等」に何らかの文字が記載されていれば、筆跡鑑定によってその筆者を特定し得る。
そうすると、筆跡鑑定自体も、「本件紙幣等」とセットになった、ねつ造証拠である疑いが浮上する(この点は、筆者の手元資料である判例時報2566号(袴田事件特集号)からは、これ以上の検証はできない)。
5 最後に
(1) このように見てくると、最初のねつ造証拠である「本件紙幣等」の不自然さ、不合理さは際立っている。
これを説明するはずであった知人女性から、何らの実質的供述、証言を得られなかった段階で、「本件紙幣等」の証拠価値はないものとすべきであった。
それが、冷静に考えれば、自然な証拠の取捨選択である。
しかるに、確定第1審判決は、知人女性の「当公判廷に於ける供述の態度には極めて作為的なものが認められるので・・・信用できない」と判断した。
どのような供述態度であったか不明であるが、同女が、前述のように長期間身柄拘束されたことに照らすと、捜査機関に対し、好感情を持たないことは当然である。
(2) ところで、確定第1審判決は、被告人の自白調書45通のうち44通は、任意性がない、または、起訴後の取り調べであるなどとして排除したが、9月9日付けの検察官調書だけは、採用している。
この検察官調書に「本件紙幣等」を合わせれば、検察官の構図を認定でき、有罪認定に役立つと考えたのであろうか。
結論が先行している証拠の取捨選択と見られても仕方がない。
先行する「本件紙幣等」が捜査機関によるねつ造であることが明白になった場合、その事実が、後行の「5点の衣類」と「端切れ」が、ねつ造証拠であることの認定に寄与する。
先に述べた「偶然の一致排除理論」によることもできるし、後の2点の証拠ねつ造の動機、必要性が発生した、という理由で、それらのねつ造認定に利用することができる。
以上