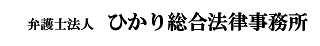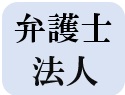金銭債権以外の権利の強制的実現の方法
私法上の権利が判決や訴訟上の和解等により確定されたにもかかわらず、それが任意に履行されない場合、民事執行という手続により強制的に権利を実現できることは、先に「民事上の権利の実現とその保全」というコラムで説明しました。
また、その権利が金銭の支払を目的とするものである場合には、債務者の財産を競売し、その売却代金から配当を受けることができる点については、「不動産競売の今昔」というコラムで実情を紹介しております。
それでは、金銭の支払を目的としない権利(不動産の明渡しを求める権利、登記名義の移転を求める権利など)については、どのような方法で強制的に実現することになるでしょうか。
これを考えるには、まず債権者が相手方に対して法律上どのようなことを求めることができるか(債務者からすれば債権者に対してどのようなことをしなければならないか)について、分析しておく必要があります。
この点に関しては、学説上、債務者が行うべき事柄の性質に着目して「与える債務」と「なす債務」に分類し、義務の内容とその履行方法に応じてそれぞれの強制的実現の方法が検討されてきました。
前者は、他人に対して物を移転することを目的とするので与える債務と名付けられていますが、債務者から目的物を取り上げて、これを債権者に移転すれば目的を達することができることから、例えば不動産や動産の引渡し(目的物の中にいる人や残置された物を取り除いて明け渡すのはその一態様です)を求める権利については、執行機関(執行官)が債務者から目的物を取り上げてその占有を債権者に移転するという方法により実現されます。
債務者の意思を無視して、執行機関により直接的に権利が実現された同様の状態が形成されますので、これを「直接強制」といいます。
なお、土地の上に建物がある場合には建物を壊して取り除かなければ土地の返還を受けることはできませんので、建物収去・土地明渡しの判決を得る必要がありますが、そのうち建物収去の部分は、与える債務ではなく、なす債務であり、後に説明する代替執行により実現されますので、土地の明渡しの直接強制と同時に執行することになります。
後者は、一定の行為(作為又は不作為)を目的とするので、なす債務と呼ばれていますが、人の行動は、作為にしろ不作為にしろ、本来自己の意思に基づき決定すべき事柄であり、これを強制的に行うことは、その主体の自由な意思に反する結果を招くため、慎重に検討することが必要です。
そこで、求められる行為の性質に照らして、その強制的な実現に適した方法を検討することになります。
まず、作為義務については、行為主体によって実現された結果(法的又は経済的見地から見た利益状態)に差異が生じない場合、換言すれば、本来の債務者以外の第三者が行っても同様の結果が得られる場合には、行為主体の個性を厳密に考える必要はないことから、執行機関の関与の下に第三者が当該行為を債務者に代わって実現するという方法が適当です。
このような第三者が代わりに行なうことができる義務を「代替的作為義務」といい、これを強制的に実現することを「代替執行」といいます。
例えば実例の多い建物の収去の場合には、債権者が執行裁判所に申し立てて、債務者以外の第三者(通常は執行官が作為実施者に指定されます)に実施させることを債権者に授権する旨の決定を発令してもらい、この決定に基づき上記の作為実施者が債務者に代わって建物の収去を行います。
これに対し、本人が一定の作為をすることに特別の意味がある場合、すなわち、債務者自身が行わなければ目的を達成できない(法的・経済的に異なる結果となる)ため、その行為を他の者が代替できない「不代替的作為義務」(出演したり、執筆したりする義務がその典型です)については、上記のような方法を採ることはできません。
そこで、このような場合は、不履行に対して金銭的な不利益を与えることによって心理的に履行を強制する方法が考えられます。
債務者にとっては、履行しない限り金銭を支払わなければなりませんので、間接的に履行を強制されることになります。
これを「間接強制」といい、具体的には、執行裁判所に申し立てて、債務者に一定の期間内に作為をすべきこと、これを履行しない場合には、一定額の金員又は不履行期間に対応する金員を支払うべきことを決定してもらい、命じられた債務を履行しないときは上記の間接強制決定に基づき債務者から金員を取り立てることになります。
なお、この心理的な強制による方法は、汎用性があることから、上記のような場合に限らず、直接強制や代替執行が可能な場合にも、併用することが認められています。
次に、ある一定の行為をしないことを目的とする義務、すなわち「不作為義務」に違反した場合には、その結果としての違反状態を是正し、あるいは将来そのようなことが行われないような措置を執る必要が生じますが、それについても本来の債務者に代わって第三者が行うことができる場合には、上記の代替執行が可能です。
また、将来の違反を禁止すること自体に関しては、その履行としての不作為は本人自身でなければ行うことができない事柄ですから、上記の間接強制の方法を採ることになります。
さらに、なす債務のうち意思表示をすべき義務、例えば、登記手続(所有権移転登記、抵当権設定登記、これらの抹消登記など)をすべき義務については、他の場合と異なり、判決や和解調書等が存在すれば、これにより義務の履行を擬制できるため、ことさら強制的に履行を図る必要はありません。
具体的には、登記は通常登記権利者と登記義務者の共同申請に基づき行われますが、判決等の債務名義に基づく場合には登記権利者により単独申請が可能です。
以上のような考え方の下、民事執行法は、金銭債権以外の権利の強制的実現の方法について次のようなメニューを用意しています。
〇 引渡・明渡義務
・ 不動産の引渡義務・明渡義務=直接強制(168条)+間接強制(173条)
・ 動産の引渡義務=直接強制(169条)+間接強制(173条)
・ 第三者占有物の引渡義務=直接強制(170条)+間接強制(173条)
〇 子の引渡し=直接的な強制(174条1項1号)+間接強制(174条1項2号)
〇 作為義務
・ 代替的作為義務=代替執行(171条1項1号)+間接強制(173条)
・ 不代替的作為義務=間接強制(172条)
〇 不作為義務
・ 違反行為の結果の除去のための代替執行・将来のための適当な処分の代替執行(171条1項2号)+間接強制(172条)
・ 不作為義務に違反するおそれのある場合の予防的処分(差止め)=間接強制(172条)
〇 意思表示義務=意思表示の擬制(177条)
なお、実際の強制執行事件の動向をみると、非金銭執行事件の中では、不動産明渡執行事件が圧倒的に多く、その中でも建物明渡執行事件が多数を占めています。
土地明渡執行事件については、建物収去に関する代替執行事件も並行して申し立て、同時執行をすることになりますが、両者ともに例年一定程度の申立てがあり、実務上も典型的な執行方法となっています。
間接強制については、従前はさほど多くありませんでしたが、家庭裁判所の審判により命じられた面会交流について監護親により実施を拒否された非監護親が申し立てる事例が注目を集め、また、いわゆるプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示命令や民事保全(仮地位仮処分)としての発信者情報開示命令の強制執行のための申立てが近年急増しているのが特徴的です。
原告として裁判を提起して勝訴判決を得ても、残念ながら、被告がその履行を拒む事態がないとはいえません。
このような場合、権利は、実現されなければ、絵に描いた餅に過ぎませんので、強制執行について検討することが必要です。
以上