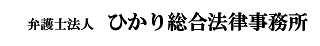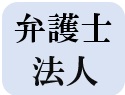建築請負工事において追加・変更工事がなされた場合の争いについて
建築請負契約においては、施主からの希望や、施工当時には予想できなかった問題(地盤に問題があった場合など)が生じるなどの様々な理由から、施主と請負人、もしくは元請と下請との間で、当初の請負契約における工事(以下、「本工事」といいます)にはない新たな内容の工事を追加する「追加工事」や、報酬や工期、仕様などについて、本工事の内容を変更する「変更工事」がなされることがあり、その内容について裁判で争いになることがしばしばあります。
今回は、追加・変更工事に関し、裁判で争いになった場合の考え方やこれら工事を行う際の注意点などについて、周辺知識にも触れながらみていきたいと思います。
1 本工事の内容の特定
追加・変更工事の内容を判断するにあたっては、そもそも本工事がどのようなものであったかがまず重要になります。
本工事の内容が明確でなければ、追加・変更工事の内容を特定することが難しくなるからです。
本工事の内容は、工事請負契約の要素となる見積書・注文書(内訳書)、設計図書(設計図・仕様書)、工程表等により定められます。
したがって、当然のことながら、工事内容は、工事一式などの概略的な記載ではなく、内訳書や仕様書などに明確に記載しておくことが重要となります。
但し、建築現場においては、当初の設計図書通りに施工が納まることはむしろ稀であり、実際の施工にあたり請負人によって現場で作成される施工図が当初の設計図書と異なるからと言って、それがすべて追加・変更工事にあたるわけではありません。
施工の納まりによる軽微な変更は、ある程度当初の請負契約で予想されたものと言えるからです。
2 追加・変更工事契約の有無、内容の判断要素
当事者の間で、追加・変更工事の内容について、追加・変更契約や見積書・注文書が交わされている場合は、基本的に問題ありません。
しかし実際には、追加・変更の工事内容や追加変更後の報酬が、現場において、現場代理人等の工事担当者間の口約束などのあいまいな形でなされていることが頻繁にあります。
(1)注文書または見積書がある場合
追加・変更契約について、注文書が交わされている場合には、基本的には、注文が存在するという判断に働くでしょう。
一方で、注文書はないが、請負人の見積書は存在するというケースがあります。
この場合、見積書通りの内容の工事を合意していたとは限らないものの、注文者が、その存在を認識していながらそれに対して何らの異議もないまま追加・変更工事が進められたというケースでは、追加・変更工事の内容について、黙示の合意があったものとして、見積書通りの内容が追加・変更契約として認定されることがあります。
このように黙っていることにより、契約当時の状況などが認められてしまう場合があるので、内容について反対や疑問点がある場合には、書面に残しておくことが必要です。
(2)注文書も見積書もない場合
注文書や見積書がなくても、当事者間のメールを有力な証拠として、追加・変更契約の合意が認められるケースもあります。
但し、メールはあいまいな表現をとっている場合が多いこと、メールを送受信している当事者が必ずしも追加・変更工事について権限を有しているわけではないことなどの事情もありますので、メールのやりとりだけで追加・変更工事を合意することは避けるべきです。
また、工事現場で行われ、文書として保存される打合せ議事録や、工事に関する当事者間のやりとりを証するファックス書面などの内容が追加・変更工事の存在の証拠となるケースもあります。
打合せ議事録等は、追加・変更工事の存在自体を立証するものになり得ると同時に、追加・変更工事の具体的内容を特定することにも役立つ場合があります。
有償であることを前提として打合せがされている場合には、有償性を示す根拠ともなり得るでしょう。
一方で、請負人が追加・変更工事を主張したとしても、打合せ議事録に追加・変更工事を前提とした記録が残されていない場合には、追加・変更工事の存在を否定する方向に働きます。
(3)見積り落ちの場合
請負人が主張する追加・変更工事の内容について、注文者が、工事があったことは認めるものの、それは本工事に含まれており、追加・変更工事にはあたらないという主張がなされる場合もあります。
このパターンは、サービス工事や手直し工事であるという主張もあり得るのですが、請負人が一部工事に関する見積もりを落としてしまう、いわゆる見積り落ちが問題になることもあります。
見積り落ちについては、当該工事の内容として当然に予想される工事について、施工の専門家である請負人が、見積もりから外してしまったなどの事情が認められる場合には、見積り落ち部分を追加工事と認めることはできないのが原則です。
但し、当初の注文者の指示が不正確であることが原因で、合意した工事の内容を超える範囲の工事が発生したような場合など、見積り落ちをしたことについて、注文者にも一定の責任があるような場合には、見積り落ち部分の工事代金の請求が認められることもあります。
3 裁判所における専門家の判断
建築工事に瑕疵があるかどうかなどの裁判においてしばしば問題となりますが、追加・変更工事が争いになる場合でも、その内容が、地盤や構造耐力等専門的な分野に関わる場合などは、法律の専門家である裁判官だけの判断では足りず、一級建築士など、建築関係の専門家の助けが必要となることがあります。
このような場合、建築関係訴訟では、調停委員、専門委員の制度が用意されています。
調停委員の制度は、民事調停法20条に基づいて、裁判所が事件を調停に付す(付調停)という決定を行い、建築の専門家である調停委員が事件に関与する制度です。
調停委員は、当事者の主張立証内容を聴取した上で、専門的知見に基づき事実を調査しながら、当事者に紛争解決の方法を提示します。
専門家の意見が入ることにより、話し合いが促進され、調停が成立することもあります。
主張がある程度整理された後(追加・変更工事が複数ある場合には、追加・変更工事一覧表などにより主張を整理することが求められます。)であれば、現場で調停を行い(民事調停法12条の4)、現地を調査することも可能ですので、技術的・専門的な内容を裁判所に理解してもらいたい場合には、調停委員の制度をうまく利用することを考えてもいいと思います。
一方、裁判所が専門的な知見に基づく説明を聴くために、当事者の意見を聴いて、専門委員を選任して、争点整理、証拠調べ、和解等の訴訟手続において、専門的知見に基づき説明してもらうという制度もあります(民事訴訟法92条の2~)。
専門的知見に基づいて説明するという点では、調停委員も専門委員も同じですが、調停委員は意見を述べることができる点、調停委員は当該事件について当事者に紛争解決を提案することができる点で専門委員とは異なります。
4 建築会社としての変更契約作成の必要性
上記で見た通り、変更契約が存在しないことにより、無用なトラブルが生じ、訴訟にまで発展しているケースが数多くあります。
そもそも建設業法は、工事内容や請負代金の額等、請負契約の締結に際して必要な事項を書面に記載し、相互に署名捺印の上交付しなければならないことを定め(建設業法第19条1項)、更に、「請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」(同条2項)として、変更契約も書面で締結することを要求しています。
変更契約は、ある程度まとめた上で、工事が終わる直前に書面化すればいいという考えになりがちですが、建設業法ガイドラインでは、工期の変更や追加工事の着工前に、変更契約の書面を作成することが要求されており、追加工事等の内容を直ちに確定できない場合でも、作業内容等を記載した一定の書面を取り交わすことが要求されています(令和4年8月国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン第8版」)。
変更契約と言っても、それほど複雑な内容を記載するわけではなく、原契約を特定したうえで、追加する工事の内容や変更する工期・報酬等を記載して当事者が記名押印するだけですので、特に、下請負人に対する指導など、建設業法で責任が加重されている特定建設業者にあっては、変更契約の作成について十分な配慮をすべきです。
以上
問い合わせるにはこちら