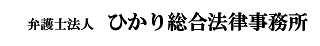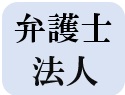患者側弁護士が医療事件に取り組むときの意識と発想
1 私は、弁護士として医療事件(医療過誤事件)に取り組むようになってから25年以上が経ちます。振り返ってみたら25年が過ぎていたという印象です。
私の弁護士業務は、医療事件以外の案件の取扱いも少なくありませんが、本稿では、私が患者側で医療事件に取り組む際に感じていることや意識していることを感想文的に述べさせていただきます。
あくまでも私個人の思いや意識になります。
2 「案件ごとの個別性」が大きいこと
弁護士が取り扱う業務は、紛争案件であるか否かを問わず、同じものはありません。
全く同じ案件のように見えても、どこかに違いがあり、また相談者(依頼人)の個性や価値観も様々です。
弁護士が案件に取り組むにあたっては、相談者(依頼人)の個性や価値観にも配慮する必要があります。
つまり、弁護士業務はオーダーメイドでなければなりません。
この点で、弁護士業務にはAIには代替できない部分がある(残っている)と思います。
そして、弁護士業務の中でも、医療事件はとりわけ個別性が大きいと思います。
人間の身体に起きた(不幸な)出来事を問題にしますが、患者の年齢・性別・病歴・病状、そして具体的な医療行為とそれによる反応や変化は人によって異なります。
また、発生した(不幸な)出来事に対する医療機関の対応は様々です。弁護士が業務として取り組む案件の進行においても、医療機関による説明の内容・程度、それと関連する対応(示談交渉や訴訟における主張内容等)は区々で、その都度、相談者(依頼人)と協議しながら慎重に進めることになります。
3 相談者(依頼人)にとっての「期待と解決(案件の終了)のズレ」
医療事件における相談者(依頼人)の期待は、「真実を知りたい。
そして、医療機関に非がある場合には、誠意をもって謝罪してほしい。」ということが多いです。
ただ、生身の人間の身体に起きたことを、事後に完全に明らかにすることは困難(ほとんど不可能)です。
当然ですが、再現することはできません。
医療機関から可能な限りの情報と説明を提供してもらうこと、いわば「情報の獲得」によって(制約はあるものの)どこまで真実に近づけるのか、ということを目指します。
依頼人の「納得感」の向上にできるだけ努めることになります。
他方で、法律上の解決は金銭賠償が基本です。
医療機関の「過失」や「因果関係」という規範(評価)を伴う要件を「賠償金額」という数字にどこまで反映することができるのかという問題です。
被害内容によるとはいえ(例.死亡か、後遺症か、その他か)、患者側に支払われる金額の大小が医療機関の行為の問題性を客観的に示すという面がありますが、相談者(依頼人)が弁護士に依頼した時の期待値と整合しているのか、常に気になります。
4 「起きたことを具体的にイメージ」すること
医療事件に取り組む際には、医療記録や医療機関側の説明書面をていねいに読み込みます。
特に、医療記録については、読むたびに新たな発見があることが多いです。
そして、集中して読み込んだ医療記録と相談者(依頼人)の説明を基に、具体的な医療行為の場面を思い浮かべます。
目をつぶって具体的な出来事(例えば、血管の壁を力を入れて不用意に削り過ぎてしまったとか、認知症の患者が要領を得ない言葉を発するので医師や看護師が厄介に思って適切な対応を怠った等)をイメージします。
論理的でないかもしれませんが、私はこのイメージをとても大切にしています。
代理人弁護士自身が、医療行為が行われた具体的な場面やその際の問題点(つまり過誤)のイメージ(「勝訴のイメージ」といってよいでしょう。)を持てない場合には、その案件は責任追及がむずかしいと思います。
見方を変えれば、医療行為の問題点の具体的なイメージ(「勝訴のイメージ」)を持てれば、それを医師に対する尋問における質問(医師の回答を踏まえて、とっさの対応(質問))や、弁論準備手続や和解における裁判所への説明と説得に活かすことができます。
自分の頭と体から出てくる発想や感覚というものです。
5 我慢と忍耐と根気強さ
医療という専門性が高いテーマについて、文献等を調べながら多くの資料を検討して悩み考え、それを文章にするという作業には負担が伴います。
特に、複数(多数)の医療事件を同時に抱えている場合には(むしろ、これが常態化しています。)、被告(医療機関)からの詳細な準備書面と膨大な医療記録を前にして、立ち往生しそうになります。
ただ、これまで何度も一体どうなるのだろうと思ったことがありますが、幸いにも何とか無事に業務を続けられています。我慢とか忍耐とか根気強さというものが少しは必要なのかもしれません。
6 医療事件への取り組みを続けている理由
私が思っていることや意識していることを感想文的に述べてきましたが、このような事情があるにもかかわらず私が医療事件に継続して取り組んでこられたのは、人間の身体や医療というものに興味と関心があるというのが理由の1つであると思います。
私は大学生時代には医事法を研究されていた先生のゼミに参加していました。
当時は脳死や臓器移植が重要なテーマでしたが、法律や理屈だけでは解決がむずかしいということを感じていました。
また、私は、会社から契約案件やМ&A交渉の依頼を受けることが少なくありませんが、株式の金銭評価を行う等の経済的合理性や取引スピードに優先度がおかれるこれらの案件と医療事件とでは、依頼人の発想や期待が大きく異なります。
日々、全く異なる種類の案件に取り組んでいることも、やや新鮮な発想で医療事件に取り組めている理由の1つといえるかもしれません。
7 最後に
生命や身体という大切な利益が不幸にして損なわれた(傷ついた)という事態、しかも、一般的には心身が改善すべき場所である医療機関で起きた出来事であるということから、業務のスタートの時点からとても重たい気持ちになりますが、縁あって関わることになった以上は、相談者(依頼人)の個性や価値観そしてご希望を踏まえながら、すべての案件に対して100パーセントの力を出して真摯に取り組んでいきたいと思います。
始めから80パーセントの力でよいという意識で取り組むことは、20パーセント分の意識的な手抜きということになります。
常に100パーセントを目指すのが本来の弁護士業務の姿であると思います。
以上
問い合わせるにはこちら