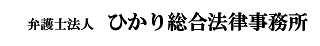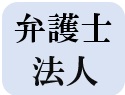企業の「コンプライアンス」について
最近、裁判所に行った際、裁判員裁判が始まって10年が過ぎたという内容のポスターを見ましたが、丁度、裁判員裁判が始まろうとしていたころ、私は検事であり、とある地方検察庁の総務部長を務めておりました。
総務部長の職務の一つに広報があり、私は、当時、これから始まる裁判員裁判の広報を担当するよう指示され、裁判員裁判について説明するため、学校、企業、地域団体等を回って講演をしていました。
その際、講演先の企業から、せっかく講演に検事を呼ぶのだから、裁判員裁判だけでなく他のテーマの講演もしてほしいという依頼があり、企業の要望を聞いたところ、「コンプライアンス」について話してほしいという要望があったのです。
当時、私は検事であり、企業法務とは無縁の世界にいましたから、何故検事に「コンプライアンス」かと思いましたが、企業から見れば、弁護士も検事も同じ法律家であり、検事でも「コンプライアンス」のことくらい知っているだろうということだったようです。
それで、私は、裁判員裁判の講演をさせてもらうため、「コンプライアンス」の講演も引き受け、「コンプライアンス」に関する本を何冊か読み、いくつかの企業で講演をしました。
にわか勉強ではありましたが、大過なく講演を果たすことができました。そのにわか勉強で獲得したことを、このコラムを借りて書かせて頂きます。
「コンプライアンス」は、一般的に法令遵守と訳され、企業が法令を遵守する経営をすることと理解されて、企業にとっては、何か堅苦しいことのように思われがちです。
未だに、「法律を守っていれば利益が上げられるなら経営は楽なものだ。」などという声を聞きますが、これは誤解です。「コンプライアンス」は、あくまで企業戦略であり、企業が、法令を遵守し、あるいは法令を積極的に利用することにより、回避できる損失を回避し、獲得できる収入を確実に獲得し、企業利益を拡大するための方策なのです。
例えば、労災事故の発生が予想される工場や現場を抱える企業は、労働安全に関する法令を遵守するほか、安全のための内規やシステムを充実させれば、労災事故を防ぐことができ、その発生に伴う損失を回避できます。
また、発明や著作を行っている企業は、特許権、著作権、商標権等に関する法令を活用し、企業の発明、著作、商標を権利化しておけば、それによって利益を上げることができます。
このようなことをするのが「コンプライアンス」です。
さらに、「コンプライアンス」の副次的効果として、法令遵守の健全経営を行っている企業ということで、企業の信用を高めることができ、それが企業の利益につながるということもあります。
「コンプライアンス」の実践として企業が行うべきことは多岐にわたり、このコラムでこれを挙げることはできませんが、「コンプライアンス」を担う部署は、総務、法務、経理、人事といった企業のいわゆる管理部門になると思います。
例えば、総務には業務上生じ得るリスクの調査とその回避策の立案をさせ、法務には業務に関連する法令の調査とその周知を行わせ、経理にはお金に関する不祥事を防止するための方策の立案と実践をさせ、人事にはセクハラ・パワハラの防止策の立案と実践をさせる等々が考えられます。
検事当時、銀行の不正融資事件の捜査を担当したことがありますが、そのときに事情聴取した銀行の融資審査担当者は、融資をする際の重要な判断要素として管理部門がしっかりしているかどうかをみると教えてくれました。
しかし何といっても、「コンプライアンス」に精通しているのは、企業法務の経験をもつ弁護士になるかと思います。多くの企業は顧問弁護士がいると思いますので、顧問弁護士が「コンプライアンス」に関する相談先になると思います。
不祥事が発生した企業や「コンプライアンス」に不安がある企業の経営者の方々は、顧問弁護士に相談されるといいでしょう。
また、最近では、インハウスなどと呼ばれている企業内弁護士を雇い入れている企業も増えつつあります。顧問弁護士と違って常勤ですので、日々発生する企業の法律問題に対応してくれるほか、正に「コンプライアンス」を担当する部署・システムの構築や「コンプライアンス」の実践の監督などを担ってもらうことができます。
最後になりますが、改めて、「コンプライアンス」は、決して、企業にとって堅苦しく、コストがかかって得るものがないというものではなく、企業が損失を回避し、獲得できる収入を確実に獲得し、企業の信用を高め、企業の利益につながるものであることを強調して、拙文の締めとさせて頂きます。
参考文献
浜辺陽一郎弁護士著「コンプライアンスの基本がわかる本」PHP研究所
以上