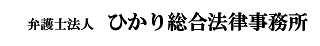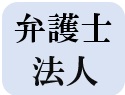国税局による査察調査
1 査察調査とは
国税庁の発表によれば,全国の国税局査察部が,令和元年度に刑事告発した脱税事件は116件であった。
中小企業や個人事業主の脱税について,国税局査察部が告発した旨の報道を耳にすることも,度々ある。
査察調査とは,国税犯則取締法に基づき,国税局査察部門が,法人や個人の「脱税」を調査する。
裁判所の令状に基づき,強制的な調査である,捜索・差押が可能である。
事前に内定調査が進められ,ある日の早朝から,一斉に,関係者のところに,強制的な調査が入ることが一般的である。
調査の結果,検察官に告発されれば,刑事事件となり,逮捕・勾留されることもある。
さらに検察官により起訴されれば,刑事裁判を受ける。
一方,税務調査は,「申告漏れ」を調査することを目的とした,所轄税務署による任意的な調査であり,事前通知がなされ,捜索・差押もない。
2 査察調査を受けたら
査察調査を受けたら,直ちに経験のある弁護士に相談することを勧める。
査察調査は,極めて特殊な領域であり,経験がないと弁護士でも適切なアドバイスは行えない。
査察調査は,客観的資料や関係者の供述に基づき,脱税容疑に対する刑事責任の立証を目的としている。
査察調査の最終段階で行われる検察官への告発が適正に行われるためには,何よりも経験のある弁護士による告発基準を踏まえた客観的資料の精査や関係者への正しい記憶の喚起が重要であり,証拠に基づく刑事裁判に持ち込むための度胸と忍耐も必要とする。
査察部の調査では,脱税容疑について一定の仮説を立てた上で,強制的な査察調査が行われることが多く,当該仮説に沿う客観的資料や供述のみが採用され,相反する客観的資料や供述は早々に切り捨てられてしまうことが散見される。
早期に,弁護士に事実の経過や認識等を話し,客観的資料の精査を受け,犯罪要件の充足の有無の観点より適切な助言を得ることができたならば,事実に反する質問てん末書が作成されて署名押印してしまうことを防ぐことができる。
見逃される又は切り捨てられる事情や証拠については,弁護士から書面を提出することができ,査察部は,刑事裁判での有罪を最終目標とする以上,無視することはできない。
強制的な査察調査の初日に受任することが重要である。
中小企業の経営者や個人事業主は,数々の困難を乗り越えた経験があり,査察調査に対しても,独りで乗り切ることができるという気持ちも,調査開始直後はあるだろう。
しかしながら,経験豊富な査察官より取調べを受け,当方に不利な証拠のみを示されたうえで,部分的に自白や同意をしているうちに,査察部が立てた仮説に沿った質問てん末書が作成されているということも少なくない。
一方で,強気に一切の調査に応じず,否定すれば,逃亡や証拠隠滅のおそれのある否認事件として,逮捕等の身柄拘束につながる重大事態に繋がる可能性もある。
不安や憤りの中で,右往左往する結果となり,事実に沿った展開とは離れていくことになり,お勧めできない。
3 税理士との連携
査察調査を受けた相談者からは,弁護士に依頼するか,査察調査に詳しい税理士(査察部出身の税理士等)に依頼するか迷っているという話をしばしば聞く。
査察調査の目的には,正確な課税も含まれており,査察調査の最終段階では,修正申告を行う税理士の関与も重要である。
また,具体的な犯罪要件の充足性の判断には,税務面での知識や査察官の裁量などの実務的な経験も重要であり,査察部出身の税理士等が調査の段階等について,経験に基づき状況を把握し,査察部門との交渉を行いやすいことも事実である。
したがって,弁護士又は税理士への依頼を選択的に考えるのではなく,経験のある弁護士と経験のある税理士が相互に連携して対応することができる体制がベストである。
なお,弊所も,査察部出身の税理士等と連携可能な体制を整えている。
その他,査察調査を受けた方は,様々な方から様々な専門家等を紹介されることもあろう。
その際には,当該専門家等が,どのように査察調査事件に関わることができるのか,どのような知識や関係性をもって事件解決に尽力することができるのか,及び,国税庁に対する税務代理を受任できるのは,税理士又は税理士法第51条に基づく通知を行った弁護士のみであることを踏まえて,慎重に検討してほしい。
4 告発率や告発範囲
国税庁の発表によれば,令和元年の査察調査の処理件数は165件,そのうち116件が告発に至っており,告発率は70.3%である。
決して,低い告発率ではないが,3割は告発に至っておらず,調査を受けたからといって,必ずしも嫌疑が固まり告発を受けると諦めるべきではない。
また,告発を受けるにしても,脱税額や範囲等に争いがある場合も多く,査察部より当初受けた指摘を全て認めるのではなく,犯罪要件を充足しない部分については争う必要がある。
脱税額や脱税の範囲は,刑事裁判になってからも,実刑や罰金額を決める重要な要素であり,査察調査開始直後より,慎重に検討していくべき課題である。
以上
問い合わせるにはこちら