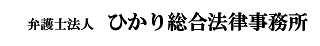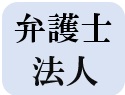建築訴訟と民法改正
平成29年5月26日に「民法の一部を改正する法律」(同年法律第44号。以下「改正民法」と略称します。)が国会で成立し,同年6月2日に公布されました。今回の改正は,これまであまり手が付けて来られなかった第3編債権関係を中心とするもので,その規律の対象となる契約が社会生活において果たす役割の重大さに鑑みると,その影響は極めて大きいということができます。その施行は,一部の規定を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが,同年12月20日に「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(同年政令第309号)が公布され,平成32年4月1日が上記の施行期日とされましたので,いよいよ現実味を帯びてきました。
私は,これまでの実務経験の中で建築訴訟に携わる機会が多く,3冊の書物(「建築訴訟」民事法研究会,「建築関係訴訟の実務」第一法規出版,「建築訴訟の審理」判例タイムズ社)に編著者として関与していますので,この改正民法により建築訴訟がどのように変わるのかという質問を受けることがあります。
建築訴訟は,建物の建築や取引に起因して生ずる紛争のうち,目的物である建物の設計,施工又は監理の瑕疵,請負工事の完成・未完成,追加・変更工事の有無,設計又は施工の出来高等に関する建築技術上の専門的事項が問題となる訴訟を指します。これら建物の設計や監理については(準)委任契約,施工については請負契約,建築された建物の取引については売買契約が関係しますが,改正民法は,売買契約と請負契約に関する条文に大きな変更を加えましたので,実務への影響が問題とされるわけです。
その最も大きな変更点は,建物に欠陥ないし不備があったときの処理ですが,現行民法の下では,主として瑕疵担保責任の問題として,欠陥ないし不備のある箇所を補修するのに要する費用を損害として代金と相殺する方法が用いられてきました。ところが,改正民法では,売買契約及び請負契約のいずれについても,「瑕疵」という概念がなくなり,新たに「目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(売買につき改正民法563条1項,請負につき同法559条による準用)との概念(以下「契約不適合」といいます。)が導入されました。したがって,契約不適合の建物の引渡しは,債務不履行として処理されることとなり,追完(修補)請求,代金減額請求,追完に代わる損害賠償請求等の問題が生じることとなりました。そのため,改正民法施行後においては,これまでの瑕疵概念を契約不適合概念に置き換え,上記の法的処理をすることになります。もっとも,従来の瑕疵概念は,売買契約及び請負契約ともに,当事者が契約によって定めた目的物の性質・形状を満たさないことであるとして捉えられていましたので,瑕疵と契約不適合の両概念の意義自体に大きな違いはないとも考えられます。そして,このことを反映して,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により,住宅の品質確保の促進に関する法律(以下「住宅品質確保法」といいます。)においては,従来の瑕疵概念が存置され(改正後の同法94条3項において,改正民法637条の規定の適用について,「不適合」とあるのは「瑕疵」とするとされています。また,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律においても,改正後の同法2条2項により「瑕疵」とは住宅品質確保法所定の「瑕疵」をいうとしています。
もっとも,目的建物が契約不適合の場合,買主又は注文者は,まず瑕疵修補等の追完請求をし,催告に係る期間内に追完がないときに代金の減額請求や損害賠償をすることになるので,従前の請負契約に関する実務上の処理のように直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償請求をするということにはならないこと,法定責任ではなく契約責任であることから,損害賠償の内容についても,信頼利益ではなく,履行利益と考えられることに注意することが必要です。
なお,買主又は注文者の売主又は請負人に対する損害賠償請求については,これまでの瑕疵担保責任に基づく場合には,債務不履行責任とは異なり,債務者の無過失による免責を認めない無過失責任とされていたのに対し,今後は債務者からの帰責事由の不存在の主張(改正民法415条1項は「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである」ことを免責事由としています。)がされることが予想されます。
また,従前,争点整理のために用いられてきた瑕疵一覧表はそのままの形では利用することができないことになりますので,瑕疵概念と契約不適合概念の異同を含めて様々な観点から検討した上で,円滑な審理の実現のための方策を整備する必要があると考えられます。
その他,売買の目的建物に瑕疵がある場合の瑕疵担保責任の権利行使期間について,現行民法では,買主が隠れた瑕疵を知った時から1年,建築請負の目的物が注文者に引き渡された時から5年(木造建物等)又は10年(鉄骨造建物の場合等)とされ,瑕疵によって建物が滅失又は損傷した場合は,その滅失または損傷した時から1年以内に限ると規定されていましたが,改正民法では,このような瑕疵担保責任に特有な時効規定が削除され,その代わりに,買主又は注文者は契約不適合を知った時から1年以内にそのことを売主又は請負人に通知しておかないと,後で契約不適合の責任を追求できないとする契約不適合通知期間制度が新設されました(改正民法566条,637条)。そして,瑕疵担保責任に関する特別な時効規定の削除により,契約不適合の責任については,一般の債権の消滅時効規定が適用されることになり,一般の債権の消滅時効は,現行民法では,権利を行使することができる時から10年であったのが,改正民法は,それに加えて,債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年で時効が完成するという,二重期間を導入しました。さらに,従来,商行為から生じる債権には商法により商事消滅時効として5年の短期時効が定められていましたが,この規定は削除されることになりました。一方,建物の設計,施工及び監理に関する債権について,これまでは3年の短期消滅時効の対象となっていましたが,これも削除されました。建物の欠陥ないし不備により被害を受けた場合には,売主や施工者等に対し,不法行為に基づく損害賠償請求がされることも少なくありませんが,改正民法は,被害者が損害及び加害者を知った時から3年,これを知らなくても不法行為の時から20年という定めを維持したうえで,この20年という期間につき,時効であることを明示しました(改正民法166条)。
以上のことは,改正事項の一端を示すにすぎません。新たにどのような問題が起きてくるのかを予測しながら,改正民法の趣旨を踏まえ,適切な処理ができるように備えておく必要があります。施行まであと2年余となりましたので,我々実務家にとっては,早急に対策を講ずる必要があることになります。